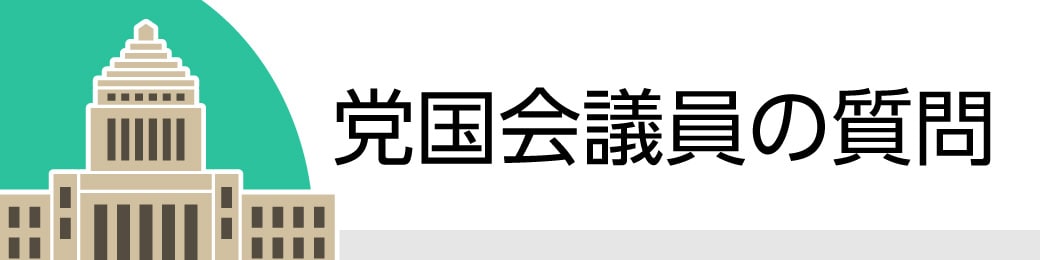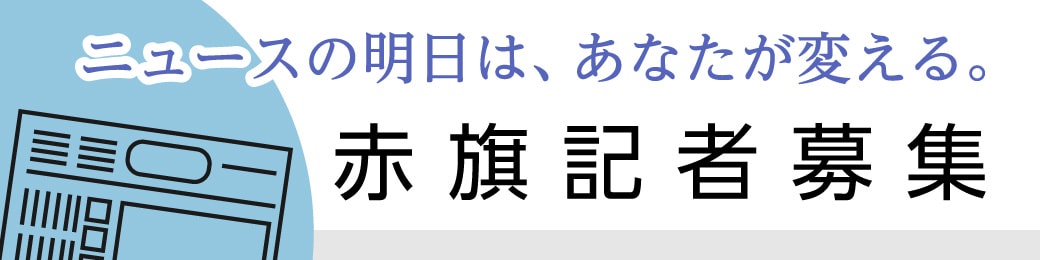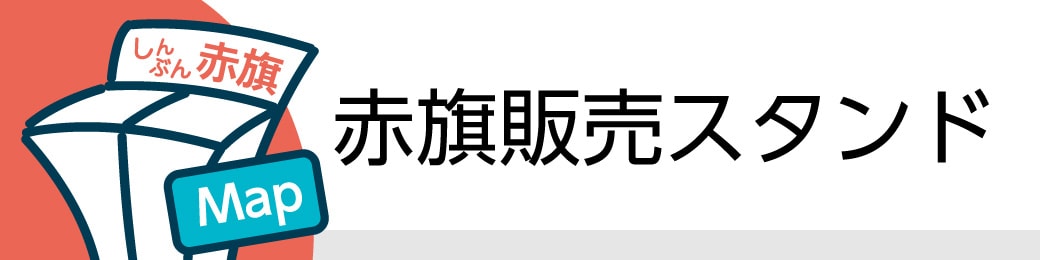2023年4月10日(月)
主張
税務相談停止命令
納税者の権利守る制度確立を
所得税法等の改定が3月末の参院本会議で与党などの賛成多数で可決・成立しました。「税理士でない者が税務相談を行った場合の命令制度の創設等」(命令制度)が盛り込まれた改定税理士法も含まれています。命令制度創設は、暮らしを壊し大軍拡を推進する2023年度予算や、中小事業者に負担を強いる10月からのインボイス導入と軌を一にした法改悪です。日本共産党は改定に反対しました。
悪用許さない論戦と運動
命令制度は、税務相談を停止させる権限を財務相に与え、停止命令を出すかどうかを調べる質問検査権を国税庁・税務署に与えます。違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科され、命令の内容がインターネット上で3年間公開されます。
財務相や国税庁長官は広範で過大な裁量権を持つことになります。課税庁側が恣意(しい)的に介入し、その権限を乱用して納税者同士の相談活動を取り締まるために悪用されることがあってはなりません。
全商連や農民連、生活と健康を守る会をはじめ、自主申告運動を弾圧する悪法を阻止する共同が急速に広がり「納税者の権利擁護を求める緊急請願署名」は3カ月で16万人分を超えました。
国会論戦で日本共産党は、停止命令の目的と対象を限定させ、今後の活動に生かせる答弁を引き出しました。財務省は、命令制度の究極的な目的は▽不正に国税を免れさせることで納税義務の適正な実現に重大な影響をおよぼすことの防止▽脱税指南で不特定多数が脱税する行為の防止―と述べました(田村貴昭衆院議員への答弁=2月21日の財務金融委員会)。
小池晃参院議員の質問には、命令制度が「納税者同士で一般的な知識を学び合うような取り組みを対象にするものではない」と答えました(3月17日の財政金融委員会)。命令処分には(1)税務相談の内容が脱税や不正還付の指南に該当し(2)納税義務の適正な実現に重大な影響をおよぼす場合―という二重の制約があり、命令処分の前に弁明(反論)の機会が与えられることも小池氏の質疑で明らかになりました。
税金について相談し、教え合うことを財務相が厳罰で「停止」させることは許されません。「納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則」と定めた国税通則法16条に反します。
市民による自由な税務相談を規制し、税理士の独占業務としている税理士法のあり方も問われます。諸外国では、税理士以外の税務相談を禁じていません。むしろ学生ボランティアなどが税務援助する仕組みを充実させています。
憲章の制定は世界の流れ
日本では人権無視の税務調査や徴収が横行しています。しかし、納税者の権利を尊重した税務行政が世界では当たり前です。
国際租税協会(IFA)バーゼル総会報告(15年)は、国際的な納税者の基本的権利の保護のために、納税者権利憲章の制定が「ミニマム・スタンダード(最低基準)」としました。経済協力開発機構(OECD)に加盟する主要国で納税者権利憲章が制定されていないのは日本だけです。
税務行政のあらゆる面で適正な手続きを貫くこととともに、人権を保障する納税者権利憲章の制定を求めていきましょう。