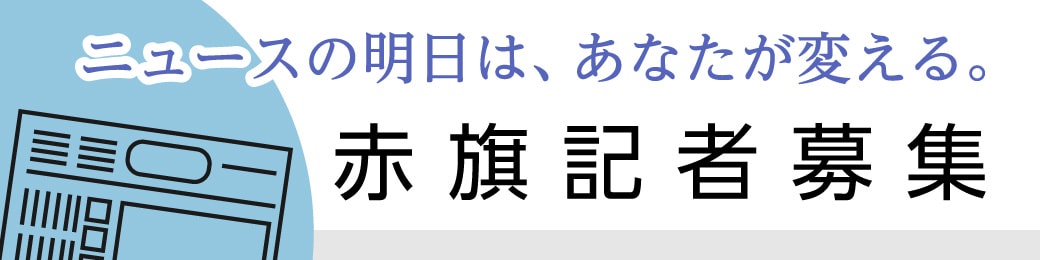2021年8月19日(木)
きょうの潮流
脳性まひで障害のある小森淳子さん(56)は1984年、ある国立大学をめざしていました。2次試験直前、大学事務局から電話が。「受験に来ないで。身体検査とか面倒だし、障害者を入学させたくないのです」▼その理由は「障害者は大学教育を受けても高額納税者になれないし、国は元を取れないから」。あまりの衝撃に返すことばもなかったと小森さんは振り返ります。障害者の社会への「完全参加と平等」を掲げた国際障害者年から、わずか3年後のことでした▼その後、小森さんは視覚障害のある男性と結婚。2人目の子どもを妊娠すると、親族は「なんで2人も…」と冷ややかな目を向けました。役所の職員は「障害者が子どもを欲しがるのはわがままだ。自分のわがままのために2人の人間を不幸にした」と▼旧優生保護法下で不妊手術を強いられた障害者らが個人の尊重を基本とする憲法に反すると国を訴えた裁判では、原告敗訴の連続です。被害から20年以上が経過しており賠償請求権が消滅しているからと▼旧法は96年、廃止に。しかし、障害者を劣ったものとする優生思想や国の優生政策で助長された障害者への差別偏見はいまだに根強く残ります▼昨年7月の東京地裁判決は国際障害者年や旧法廃止をあげ、そのころには日本からは障害者差別はなくなっていたから提訴できたはずだと。その時代に差別や偏見に抗(あらが)いながら生きてきた小森さん。こうした現実に司法は目を向けるべきです。今年は国際障害者年から40年です。