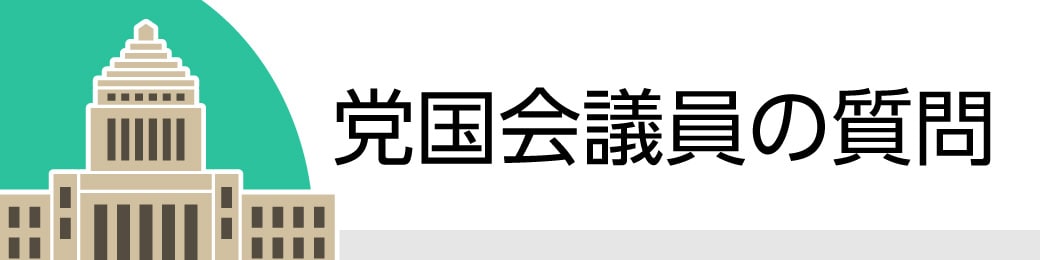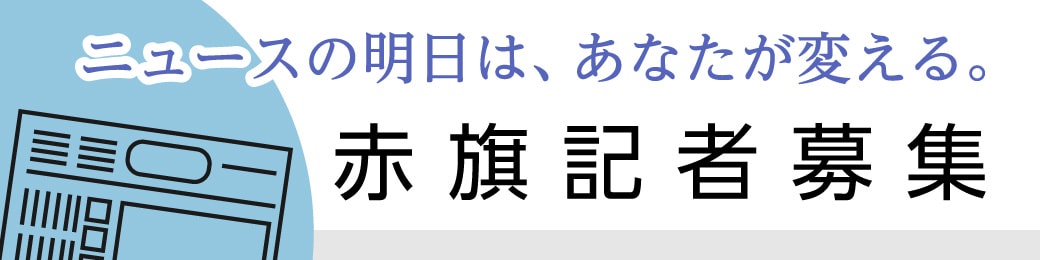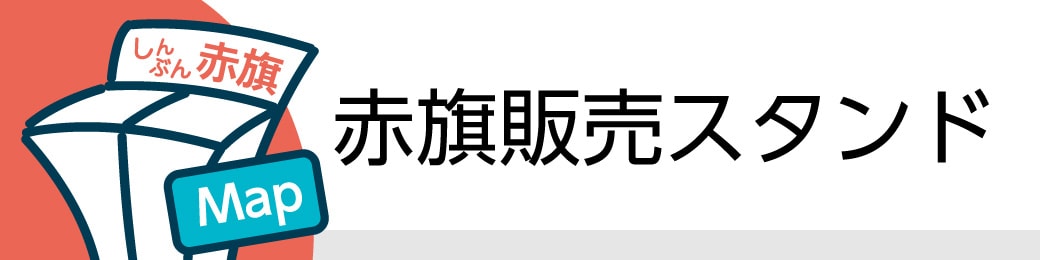2025年6月17日(火)
主張
7社の共同宣言
「日米同盟」とメディアの見識
国連憲章も、国際法も平然とかなぐり捨てるトランプ米大統領の振る舞いを目の当たりにし、大手メディアでも危惧や批判の論調が目につきます。しかし日本を対米従属に縛りつける根源・日米同盟そのものを問うことはしません。日米同盟の呪縛にいつまで囚(とら)われるのでしょうか。
■致命的弱点を持つ
もともと政府は安保条約が軍事同盟であることを隠すため「日米同盟」という言葉を避けてきました。新安保条約を審議した1960年の国会でも、「いわゆる軍事同盟というべきものでない」(岸信介首相)と答弁してきました。
80年代に入って、初めて日米を「同盟関係」とした日米共同声明が出されましたが「軍事的意味があるかどうか」をめぐって紛糾し、外相が辞任する騒ぎにもなりました。
しかし今日では、メディアは日米同盟を不可欠な存在とし、当然視しています。
メディアの最大のタブーは安保条約=日米軍事同盟に異議を唱えることです。その象徴が、65年前の今日、安保闘争の高揚のなか1960年6月17日に出された、「朝日」、「毎日」、「読売」など新聞7社共同宣言です。高揚する安保闘争の「事態収拾」を訴え、闘争の終息を求めました。岸首相は、新聞社首脳と会談を重ねていました。権力に迎合し、安保条約を擁護する日本のメディアの致命的な弱点をさらけだす出来事でした。
今日、確かにメディアはトランプ大統領に危惧の声をあげ、なかには大軍拡など米国に追随する日本政府への批判もあります。しかし日米同盟そのものを大前提にし、その枠をこえることは視野にありません。むしろ日米同盟の強化を求める論調が主流です。 石破茂首相とトランプ大統領の初会談(2月)をめぐっても、「日本外交の自立性を」と地位協定の改定にも言及しますが、それは「同盟をより安定させるため」と位置づけられます(「朝日」社説)。また「米国をどこまで頼りにできるのか」と問うても「守りの多くを米国に委ねざるを得ない現実」があり、「核兵器を含む戦力を用いて日本を守る『拡大抑止』の強化をうたったのも妥当だ」(「日経」社説)という具合です。
大軍拡など理不尽な要求をなぜキッパリ拒否できないのか。その根底には日米同盟の呪縛があります。
■軍事同盟なくす道
日本共産党は安保条約をなくし、対等・平等・友好の日米友好条約を求めています。もちろん軍事同盟が存在するもとでも絶対に戦争を起こさせない政策や運動はきわめて大切です。日本共産党の「東アジア平和構築の提言」も軍事同盟への賛成・反対の立場を超えて、平和の地域をつくってゆく提唱です。
しかし、いま、トランプ大統領登場のもと、外交の「自立」を求める国民世論に応え、軍事同盟をなくす道があること、それが国際的にも大きな流れに成長していることを提起していくことがいよいよ重要になっています。
戦後80年。メディアはいったいいつまで外国軍基地の駐留を認め、国家的な従属を是とするのでしょうか。見識と勇気が問われています。