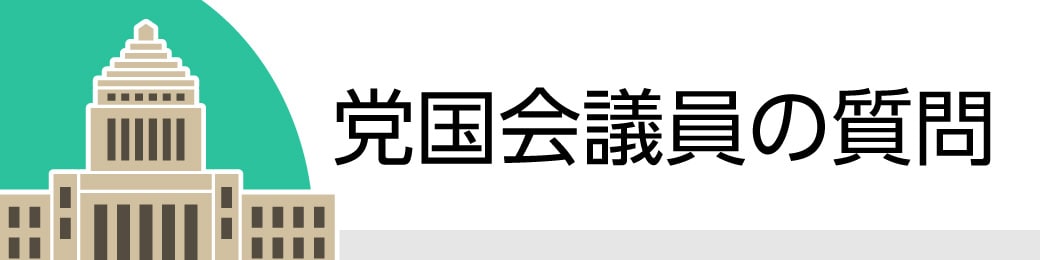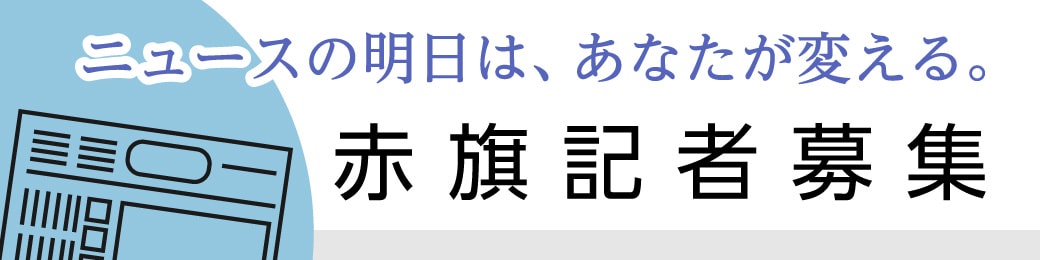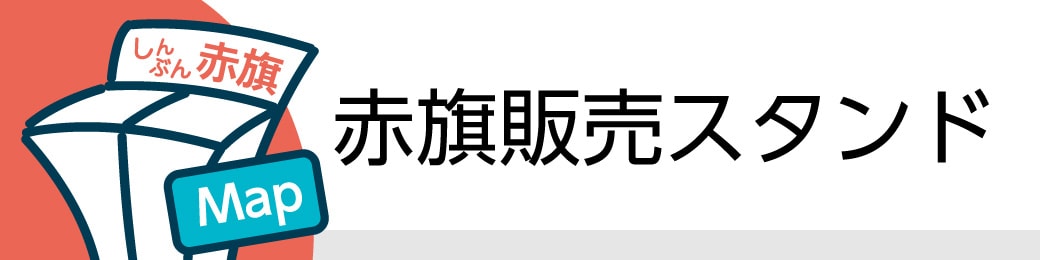2025年3月21日(金)
能登地震 豪雨災害
共同支援センターが生産米買い取り支援
被災農家「困っている人に使って」
全国的に米不足が問題となっているなか、能登半島地震が発生した石川・能登では引き取り先が見つからない生産米が籾(もみ=玄米に変える前の米)のまま大量に残されています。「能登半島地震被災者共同支援センター」は、昨年豪雨災害を受けた石川県輪島市の農家を訪問し、生産米を買い取って被災者への支援米として活用する支援を行いました。いまだに電気が復旧せず、米の籾摺(もみす)りができずに処分に困っていた農家は「とても助かる。困っている人に使ってもらえてうれしい」と語っています。(石川県・鈴木宏太)
 (写真)受け取った米を運び出す(右から)藤野、黒梅の両氏=19日、石川県輪島市 |
輪島市上大沢町は、能登半島地震の発生前は20世帯ほどが生活していました。震災と豪雨災害を受け、ほとんどの住民は市内の仮設住宅などで暮らしています。現在、この町で農業を続けているのは2軒です。
そのうちの1軒、Aさん(67)は農業と漁業を営みながら、輪島塗の塗師の仕事もしています。川沿いにあった田んぼは、昨年の豪雨で現在も流木や土砂が残ったままです。
同センターの黒梅明事務局長らが11日に訪問し、小屋の2階に残されていた約1200キログラムの生産米を買い取りました。Aさんは、「籾摺りができないのでどうすることもできず、農協に頼ったが受け入れてもらえなかった。困っている人に使ってもらえてうれしい」と述べました。
19日には、同センター責任者の藤野保史氏らが同市で農業を続けているもう1軒のBさん(64)を訪問し、約1500キログラムの生産米を受け取りました。「電気を待つか、処分するか迷っていた。助かります。生まれ育った場所で、残りの人生は農業や漁業を続けたい」
藤野氏は、「地震と豪雨を経験してなお、何とか能登で暮らしたいという方がたくさんいる。心から応援したい。同時に、田んぼに流れ込んだ土砂や木々がそのままの場所が残されている。国の支援を抜本的に強化すべきだ」と述べました。
黒梅氏は「こういう地域の実情を知ってほしい」と強調しました。
同センターの買い取りには、石川と富山の農民運動全国連合会(農民連)も協力。籾摺りは、石川県七尾市に住む同会員が行います。