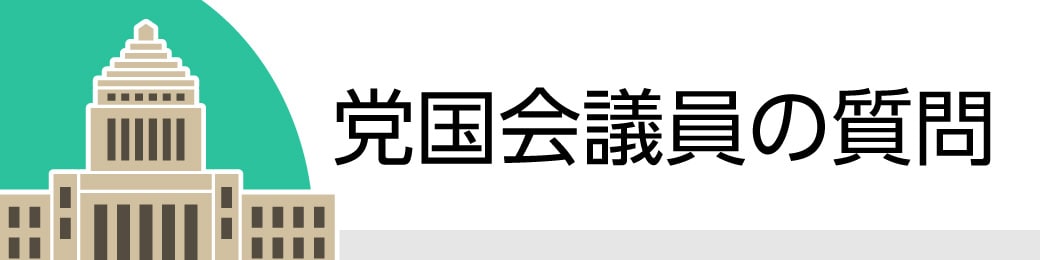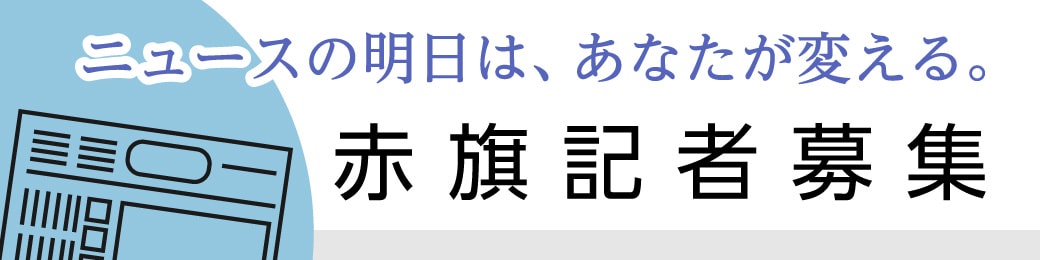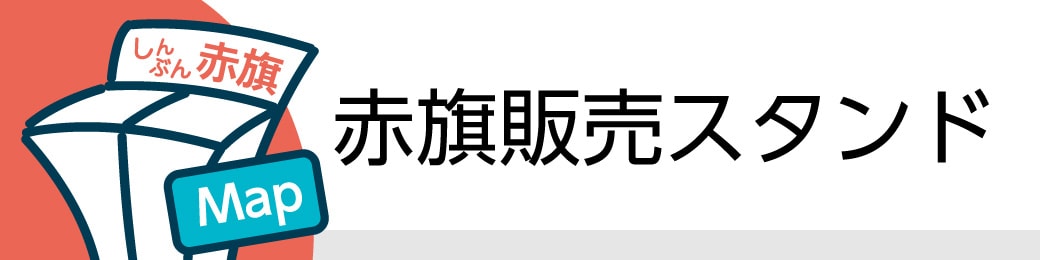2025年3月11日(火)
主張
東日本大震災14年(上)
期間終了で支援終わらせるな
東日本大震災から11日で14年です。甚大な被害に加えコロナ禍、不漁、物価高、岩手県大船渡市での大規模火災発生など、今なお支援が必要な状況は変わっていません。
国の第2期復興・創生期間は2025年度が最終年とされ、原発被災地を除き、自治体への支援は原則終了し、必要な事業は例外的に支援するとされています。
防潮堤や土地のかさ上げなどはほぼ終了しました。しかしいま、心のケアと生業(なりわい)支援、ことに漁業・水産業への支援が切実に求められています。国は支援を打ち切ってはなりません。
心のケアでは、震災後の住環境、家庭環境の変化が子どもの心に影響しています。支援を要する子どもの割合は津波被災地域で高く、岩手県こころのケアセンターの相談支援件数は23年度8千件超と震災後1年目とほぼ同じです。
■県の姿勢で違いが
必要な支援の継続では、県の姿勢による違いが浮かび上がっています。
岩手県は、全額国庫補助で行われている、こころのケアセンターや被災者支援センターの必要性を国に働きかけ、復興期間終了後も補助継続の方向で復興庁と協議中です。
一方、宮城県では3カ所ある心のケアセンターが25年度末で閉所されます。子どもの心のケアハウス、緊急スクールカウンセラー(SC)派遣事業、災害公営住宅の見守りなどの補助は打ち切りや他省の一般施策への移行による縮小が危惧されています。
心のケアハウスを利用する子ども数は右肩上がりで、国の補助打ち切りは事業継続にとって打撃です。緊急SC派遣事業への国庫負担は、文科省の一般施策になると全額負担から3分の1になります。
宮城民医連の調査(24年度)では、災害公営住宅入居者の64%が70歳以上、半数が独り暮らしで、見守りの必要性はいっそう高まっています。
国はすべての被災地で支援を続けるべきです。自治体には住民要求を国に突きつけていく責任があります。
■深刻な水産・漁業
生業の再建では、沿岸部で海水温上昇による不漁や魚種の変化が困難をもたらしています。岩手県では主要魚種のサケがほぼ取れず、サンマ、スルメイカの水揚げ量が震災前の15%程度と激減、ホタテは6%、アワビは17%です。宮城県も特産のホヤが全滅に近いなど深刻です。
取れる魚が変わり新たな機械・設備を入れると、グループ補助金の返還を求められる場合があり、復興の足かせになっています。国は柔軟な対応をすべきです。
中小事業者が二重債務に陥るのを助けるため、国の設けた公的機構が肩代わりした借金は15年間で返済とされていますが、宮城県では昨年末で50%以上が返せていません。生活再建のために借りた災害援護資金返済の滞納率は被災地全体で36%(23年9月末)と前年と変わりません。
返済期間の延長や病気の高齢者など返すめどのない人は国の責任で免除すべきです。
大軍拡をやめ、今なお必要な被災地支援に充てるべきです。復興特別所得税の軍拡財源への流用は許されません。