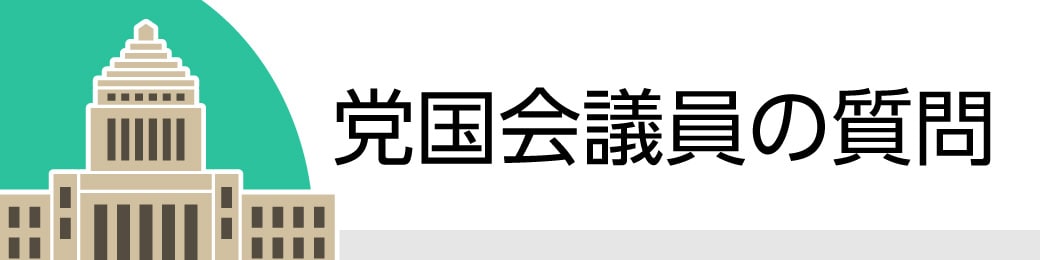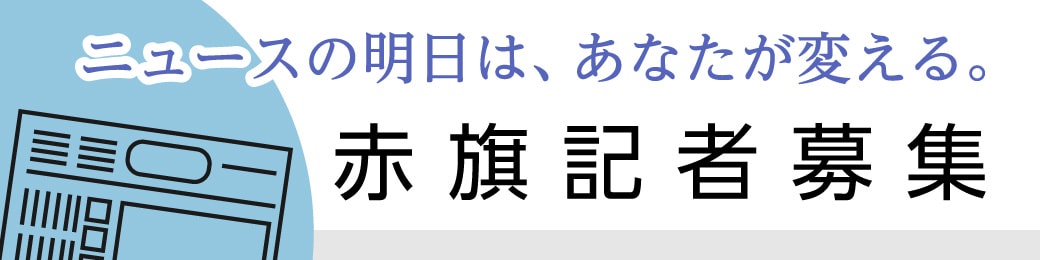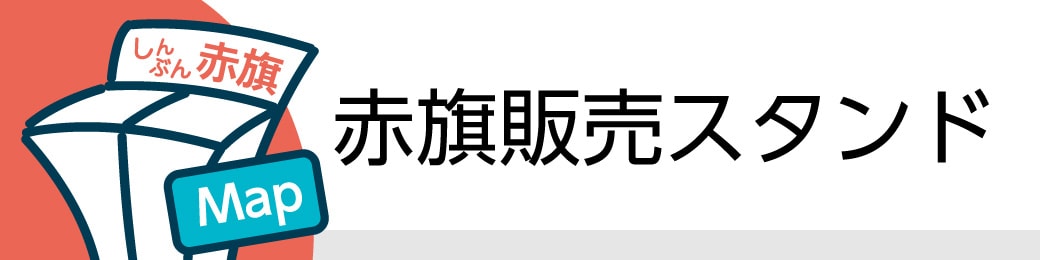2025年2月17日(月)
きょうの潮流
作家の小林多喜二は初期の作品「一九二八年三月十五日」や「蟹工船」で知られます。しかし、彼自身は過去の自作に満足していませんでした。バルザックの長編と比べ「自分の今迄(いままで)の小説が…高々(たかだか)が『綴方(つづりかた)』位(くらい)でしかなかった」とすら書いています▼時代の「芸術的概括」をめざして新たに取り組んだのが「転形期の人々」です。北海道・小樽の労働運動、革命運動の勃興期を描きます。三部作の構想でしたが、満州事変後の緊迫した情勢下、序編だけで連載は中断しました▼秋田出身の貧しい労働者・龍吉、社会科学研究会を始める古山、労働運動のすぐれた指導者・旗塚など多彩な若者が登場。その成長と活躍は、特高の多喜二虐殺によってもう見られません▼しかし彼の志は消えませんでした。例えば戦後、宮本百合子の書いた『道標』三部作は、一つの時代の芸術的概括を、多喜二にかわって成し遂げたといえるのではないでしょうか。1927年から3年間のソ連・欧州訪問と主人公の思想的成長を描いた大作です▼『道標』発表時、評論家の加藤周一はこう評しました。「一人の人物の生涯と発展を追求するという仕事は思想的立場が支えていなければできない」「共産党員でない作家に、今あれだけの仕事はないと思う」(『世界評論』50年3月号)▼多喜二は「東倶知安行(ひがしくっちゃんこう)」で「俺達の運動は何代がかりの運動だ」と書きました。文学もまた世代を超えた活動です。今年は没後92年。彼の志を受け継ぐ多喜二祭が各地で開かれます。