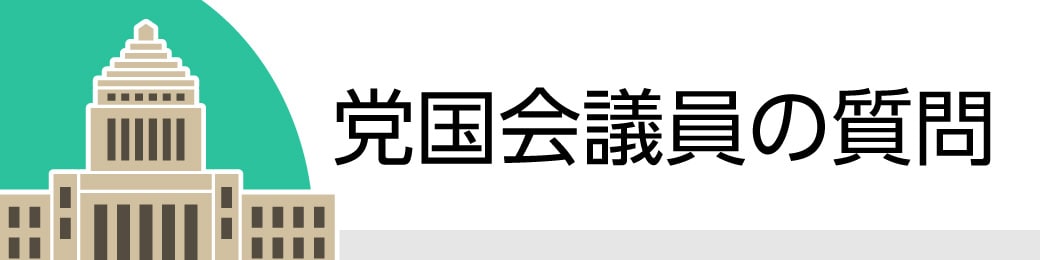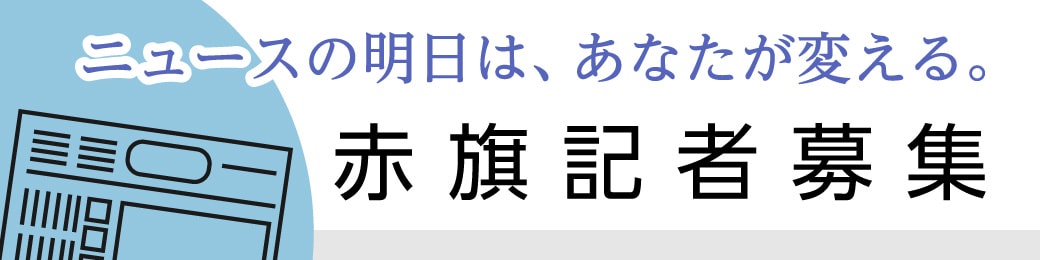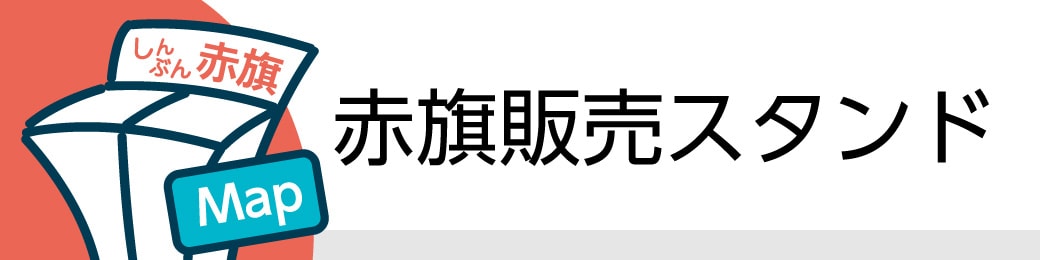2024年12月26日(木)
主張
無形文化遺産登録
日本の伝統酒造りが問うもの
飲酒の機会がふえる年末年始をむかえます。酒を酌み交わしながら、旧交を温め、英気を養う機会もつくりたいものです。
日本酒、焼酎、泡盛などは、日本の酒を造る技術「伝統的酒造り」によって生み出され、各地の気候風土に応じて発展してきました。
しかし、日本酒の国内消費はピーク時に比べ4分の1以下に減少しています。いま「伝統的酒造り」をめぐる状況は、順風満帆というわけではありません。
■保護に必要な措置
こうしたもと、日本の「伝統的酒造り」がユネスコ(国連教育科学文化機関)の無形文化遺産に登録されました。
日本の酒は、それぞれの土地、水、穀物、こうじ菌を使い、杜氏(とうじ)や蔵人(くらびと)が築き上げた技術で造られ、多彩な儀式や祭礼行事など社会に深く根ざしています。
ユネスコは、この酒造りが「日本の社会にとって強い文化的意味を持つ」と評価し、社会的結束や環境の持続的可能性にも貢献していると指摘しています。
関係者は登録決定を喜び、伝統的な酒の素晴らしさを世界に広げたいと抱負を語っています。日本の誇るべき文化的財産として日本の酒造りが継承され、発展することが望まれます。
しかし、地球温暖化による酒米づくりや発酵への影響、環境破壊による水の汚染、作り手の高齢化や後継者不足、さまざまな行事を継続させるうえで土台となる地域社会の維持、何よりも日本の農業そのものの衰退は大きな問題です。
農民連(農民運動全国連合会)によれば、地元産の酒米を育てる農家と地域の酒造業者が協力し、消費者と連携して地酒を守る動きも広がっているといいます。
無形文化遺産条約によって、政府には「保護を確保するために必要な措置をとること」が求められており、その役割が問われます。
■酒と戦争の関わり
日本の酒を考えるさい、戦争との関わりにも触れないわけにいきません。
「日清戦争、日露戦争は酒税が支えた」ともいわれます。戦争を契機に膨らんだ財政需要を満たすために酒税が増やされました。1899(明治32)年には地租を抜き、国税の税収第1位、全税収の4割を占めるまでになりました。その後、酒税は国税の中心の座を40年近く保ってきました。
日中戦争のもとで、生産統制された日本酒は添加物を加えて約3倍に増量するなど品質を落としました。
泡盛は沖縄戦で壊滅的な打撃をうけました。酒造所が集中していた那覇市首里には陸軍司令部がおかれていたため、激しい砲爆撃が加えられ、古酒(クース)の入った甕(かめ)もことごとく壊され、泡盛づくりに不可欠な黒こうじも絶滅したと思われていました。
泡盛の復活に尽力した一人、土屋實幸(さねゆき)さんは「あの戦争さえなかったら我々は二百年、三百年という古酒を味わうことができたのではないか。将来二度と戦争は起こさない平和な世をつくり、沖縄全体をクースの島にしていきたい」と語っています。(『沖縄戦と琉球泡盛』)
「伝統的酒造り」もまた日本の自然と文化を守るとともに、平和な日本であり続けることを求めています。