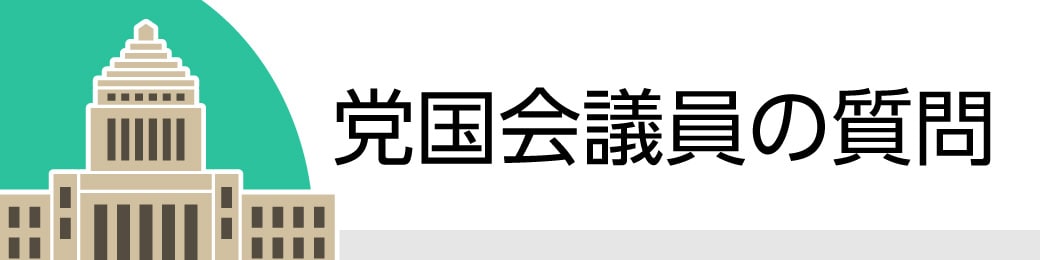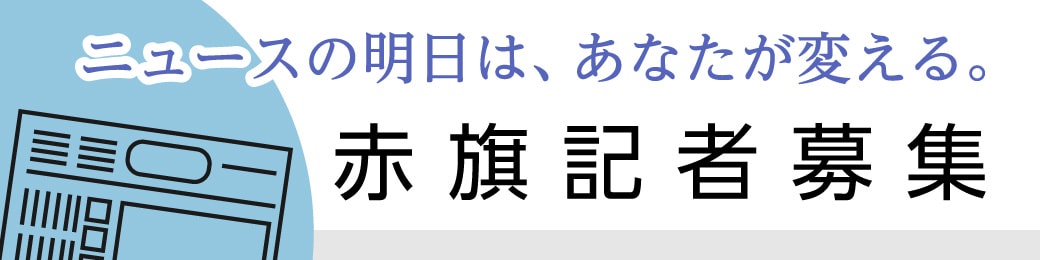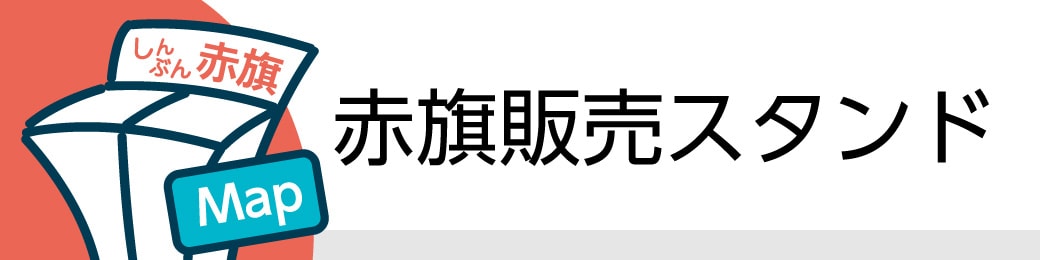2024年12月6日(金)
きょうの潮流
沖縄戦の年の暮れ。廃虚と化した酒蔵の土の中から、何かを懸命に掘り出す姿がありました。広げた蒸し米に黒麹(くろこうじ)をまぶして敷いたわらのむしろ、ニクブクです▼また泡盛をつくることができるかもしれない―首里の蔵元だった佐久本政良(せいりょう)さんは感激の涙を流しました。琉球の時代に首里三箇(しゅりさんか)と呼ばれた地域に限って製造が許されていた泡盛。しかし首里は徹底的に破壊され、酒蔵も壊滅▼奇跡的に見つけた黒麹菌を、佐久本さんは他の蔵にも分け与えて泡盛復興の道を切り開きました(『沖縄戦と琉球泡盛』)。泡盛の発展に尽くした土屋實幸(さねゆき)さんは「二度と戦争は起こさない平和な世の中をつくり、沖縄全体をクース(古酒)の島にしていきたい」と将来を見すえました▼その泡盛をふくめた日本の伝統的な酒造りがユネスコの無形文化遺産に登録されました。全国の酒蔵や杜氏(とうじ)、地震被害をうけた能登の酒造会社からも技術の伝承が世界に認められたと喜びの声があがっています▼和食や和紙をはじめ、これで国内の無形文化遺産は23件。政府はインバウンド効果につながるなどと歓迎しますが、こうした伝統文化を守るために力を注いできたのか。海外では人気が高まる日本酒も、国内の消費量は落ち込んでいます▼きのう農民連は、農林水産予算をきりすてるなと財務省に抗議しました。酒造りの土台ともなる農業が脅かされています。政府の失政、戦争や災害。この国に深く根差した文化を受け継ぎ、どう生かすか。それが問われています。