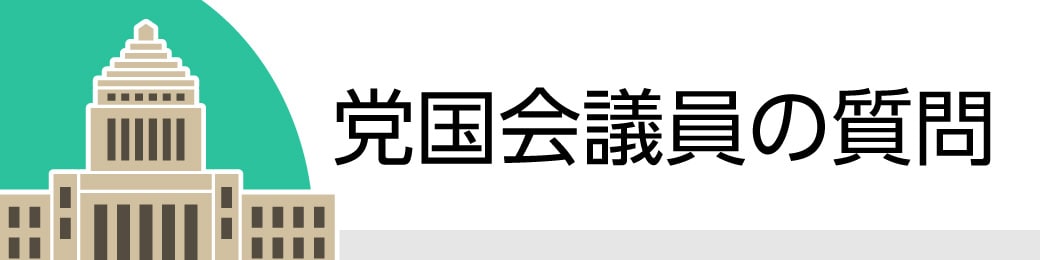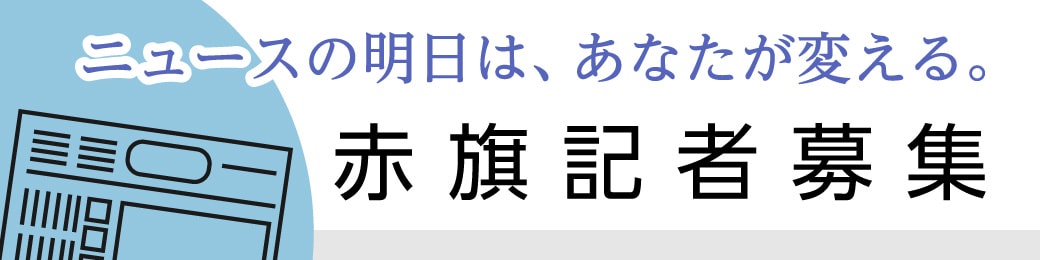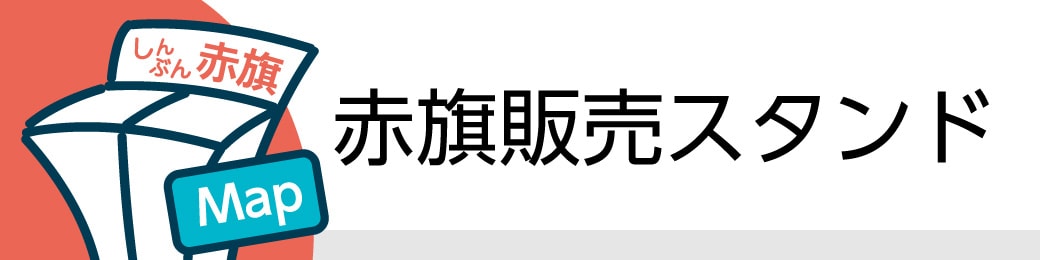2024年7月25日(木)
主張
中教審の大学再編
少子化招いた責任に向き合え
文部科学省の中央教育審議会(中教審)が、急速な少子化の中での将来の高等教育のあり方について年度内の答申に向けて審議しています。中教審の大学分科会と特別部会の合同会議が19日に開かれ、中間まとめ案が大筋了承されました。
中間まとめ案は、2040年以降の大学進学者数は現在に比べ2割減ると推計し、「高等教育の全体『規模』の適正化」が必要だとします。大学などの「再編・統合、縮小・撤退の議論は避けることができない」と強調し、個々の大学に少子化対応の責任を押し付けています。
しかし、急速な少子化の原因の一つは、重い教育費負担にあります。夫婦が理想の子ども数を持たない理由として最も多いのは「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」です(「こども未来戦略」)。こうした重い教育費負担をつくりだしたのは中教審です。その責任を自覚し、是正をはからなければ、少子化・人口減少は止まりません。
■受益者負担導入で
そもそも戦後の教育費負担の原則は「設置者負担主義」(学校教育法第5条)とされました。国立大学の財政責任は国にあり、学生に重い負担を求めることはできませんでした。
これを覆したのが「受益者負担主義」です。「教育は投資だ」と主張し、高等教育を受けることで「経済的利益」を得る学生が学費を払うのは当然だとして、中教審が1971年の答申に受益者負担主義を持ち込みました。
これを口実に学費の値上げが始まり、国立大学の授業料は71年の1万2千円から2005年には53万5800円(標準額)へと45倍に、私立大学の授業料(平均)も1971年の9万610円から2023年には95万9205円へと10倍に高騰しました。中教審はこれを反省していません。
■国民要求は無償化
国民が高等教育の将来像として求めているのは無償化です。「日経」アンケートでは少子化対策の1位は「大学までの学費無償化」でした(6月6日付電子版)。無償化は経済的理由であきらめていた若者の進学機会を保障し社会人や留学生の進学者を増やします。
中間まとめ案は、少子化による定員割れで大学の経営が悪化し、教育の「質」を維持できないからと縮小・撤退を促しています。
しかし、私立大学の経営悪化の最大の原因は、「経常費の2分の1助成」という国会決議を踏みにじって、国庫助成が1割にとどまっていることにあります。
私学助成を抜本的に拡充すれば、定員割れでも、経営を安定させ、少人数教育により教育の質を向上させることができます。定員割れの大学に対する私学助成の減額などのペナルティーは直ちに撤廃すべきです。
東京大学など学費値上げを検討する国立大学が広がっています。原因は04年の法人化後、運営費交付金が12%も削減され、物価高騰などに対応できないことにあります。削減分を回復し、値上げ回避が急務です。
高等教育機関に対する日本の公財政支出はGDP比で0・5%です。OECD(経済協力開発機構)加盟国の平均0・9%の半分です。世界最低水準の大学予算の抜本増こそ必要です。