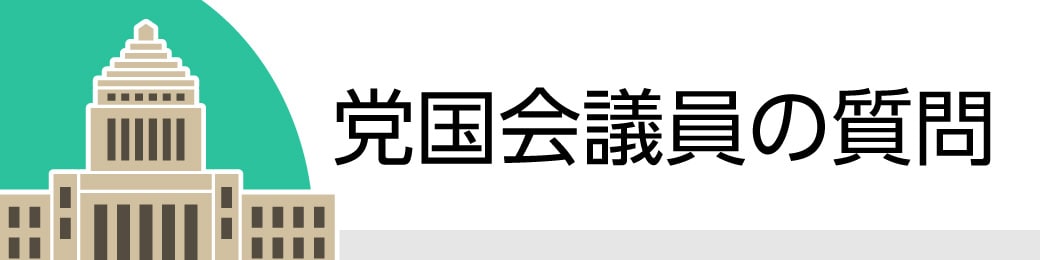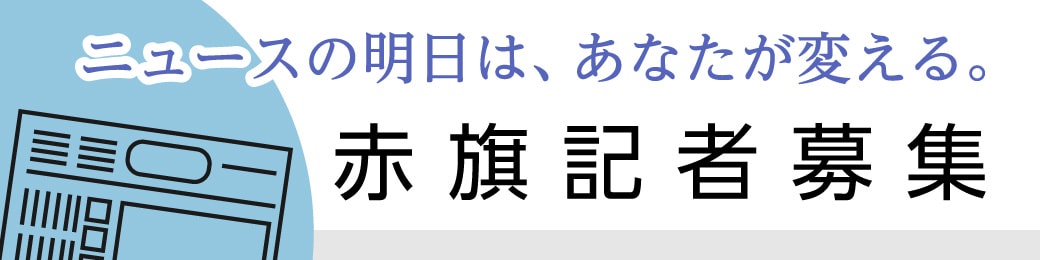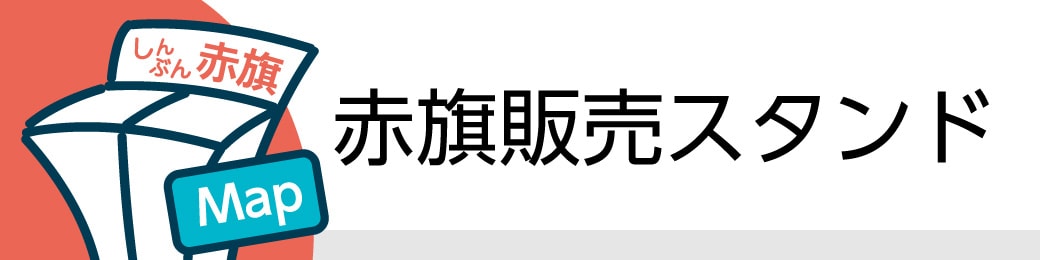2024年7月20日(土)
主張
第56回保育合研
すべての子に「育ちの権利」を
一人ぼっちの保育士をなくそう、いい保育をしようと、1969年、長野県山之内町で1842人の保育関係者から始まった全国保育団体合同研究集会(保育合研)は今年56回目を迎えます。熊本県での初めての開催です(27~29日)。近年、参加者はオンライン含め8000人規模となり、保育者、保護者、研究者など保育や子どもにかかわる人たちが全国から集まり、学びあい、交流します。
保育合研は、保育実践を学び合うとともに、いい保育をするには条件整備が不可欠だと、実践と運動の両輪で保育運動をすすめてきました。
■基準改善勝ち取る
今年、76年ぶりに保育士の配置基準が改善されました。4、5歳児の子ども30人に保育士1人から25人に1人。3歳児は子ども20人に保育士1人から15人に1人への改善です。
「子どもたちにもう1人保育士を」という保育運動が、「この配置基準では子どもの命と安全を守れない」という実態を可視化し、長年動かなかった大きな壁を動かしました。実践しながら粘り強く運動を広げ、社会を変えていく―保育合研で培われた力が、社会を動かし、国の制度を大きく前進させました。
経過措置として当面従来の基準での運営が認められており、改善の時期を不明とする保育施設が30%あります。すべての施設で早期に基準が適用され改善につながるよう国は責任をもって取り組むべきです。
配置基準改善は深刻な保育士不足の解決抜きにはすすみません。原因である低賃金と長時間労働など劣悪な処遇の改善が必要です。大軍拡ではなく、子どもたちの育ちを保障する予算を抜本的に増やすべきです。
政府は先の通常国会で「子ども・子育て支援法」を成立させました。そのなかには、親の就労にかかわらず保育所を利用できるとする「こども誰でも通園制度」が含まれており、2026年度から本格実施しようとしています。
在宅で孤立する保護者を支えることは大切です。しかし、同制度ではスマートフォンのアプリで空きを見てその都度、空いている園・時間に申し込む方式も考えられています。新しい環境に慣れるための「ならし保育」も、事前の顔合わせもないまま預けるのは、子どもにも保育士にも負担が大きく、「簡単に受け入れられるものではない」「子どもの命にもかかわる」という懸念が現場から上がるのは当然です。
親の就労にかかわらず、どこに住んでいても、すべての子に安心・安全な質の高い保育を保障し、「育ちの権利」を保障することが政治に求められています。
■つながって希望を
今年の保育合研のテーマは、「つながり、ふみだし、つくりだそう―すべての子どもの笑顔と平和のために」です。日々忙しく、子育てや保育のことで語りあい、学び合うことも薄れ、孤立しやすい社会です。
そのなかで、おとなも、保育士も、だれもが安心して保育・子育てができる社会、自分らしく生きられる平和な社会をつくるために、困難はあってもつながり、保育・子育ての希望を切り開く力になる保育合研になることを期待します。