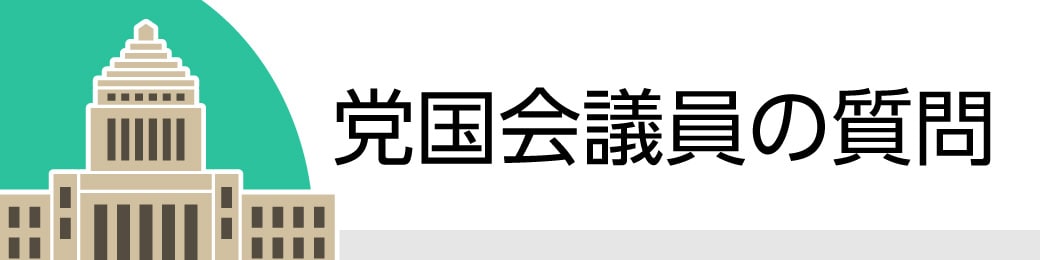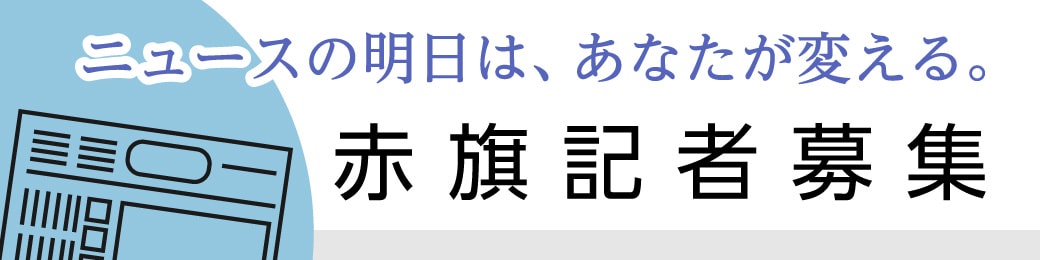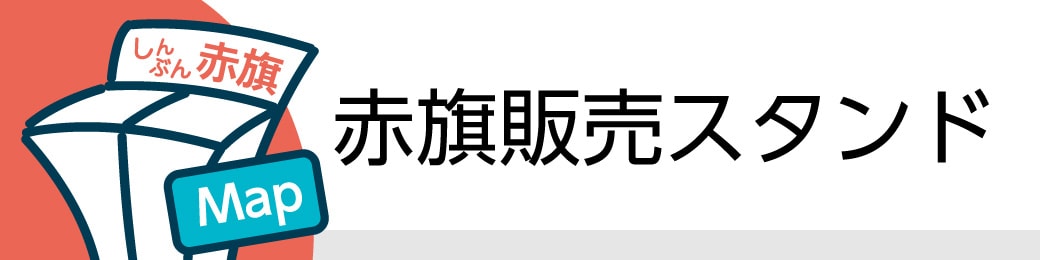2023年11月15日(水)
主張
クマ被害の急増
現場の声聞き人命守る対策を
クマによる人身被害が、統計をとり始めてから最多となりました。死者も相次いでいます。冬眠に入る時期を迎えて人里への出没が減ることも予想されますが、被害件数は増加傾向です。一過性の問題ではありません。国が住民や自治体の要望を聞き、予算、人員の確保を含めて対策を強める必要があります。
人里に近づけないために
2023年度の被害人数は、10月末までの集計で180人です。最多は秋田県の61人、次いで岩手県が42人と、両県で全国の6割近くを占めます。出没情報は秋田県で昨年の2倍、岩手県で1・5倍です。クマが市街地に現れる「アーバンベア」も頻発しています。
個体の増加と生息域の拡大が指摘されています。03年度と18年度を比較した調査では、絶滅したとされる九州と、絶滅の危険性が極めて高い四国を除いて全国でクマの分布が拡大していました。
出没が増えている原因について、環境省の「クマ類の出没対応マニュアル」は、短期的には、餌となるドングリなどの凶作をはじめ自然環境の変動、長期的には中山間地の人間社会の変化があると指摘しています。「里地における変化としては、過疎化や高齢化による人間活動の低下、耕作放棄地の拡大、放任果樹の増加等があげられます」と述べています。
林野庁によると、里地の人口は1965年度以降、50年間で4割減り、高齢化率は4倍に増えました。過疎化が進み、里山が荒廃したことで、クマと人を隔てる地域が縮小し、人里に出てくる要因となっています。
被害を防ぐため、環境省が主導して各地で「ゾーニング管理」が進められています。クマを積極的に保護する生息地、人間活動を優先する地域、その間の緩衝地帯を設定し、すみ分けを図る方法です。地域ごとに計画を立て、個体群の管理、人里への侵入を防ぐ環境整備、現れた場合の追い払いや捕獲などを行います。予算、人員の確保が十分か、問われます。
灌木(かんぼく)の刈り払いや放置された果樹の撤去には人手が必要です。電気柵の設置が有効とされますが、購入の補助金に上限があります。捕獲は危険を伴う作業です。過疎化、高齢化が進んだ地域で実情にあった支援が行われているか、点検が欠かせません。
専門知識を持った行政職員の役割は重要です。鳥獣指導員に、雇用期間が限定された会計年度任用職員を充てている県があります。自然相手の、長期にわたる仕事を担えるよう、安定した身分を保障すべきです。
国の役割が欠かせない
個体群の把握については環境省が「実施体制や予算の状況から十分にモニタリング調査が実施されていない地域がある」(特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン)としています。
北海道東北地方知事会は、住民の安全確保のためクマの生息調査や出没対策が必要だとして、財源や専門技術の支援を国に申し入れました。クマをイノシシなどと同様の指定管理鳥獣とし、捕獲費用を国の財政支援の対象にすることも求めました。
クマ被害から人を守ることと自然環境の保全、農山村の振興は一体の問題です。国が責任を果たさなければなりません。