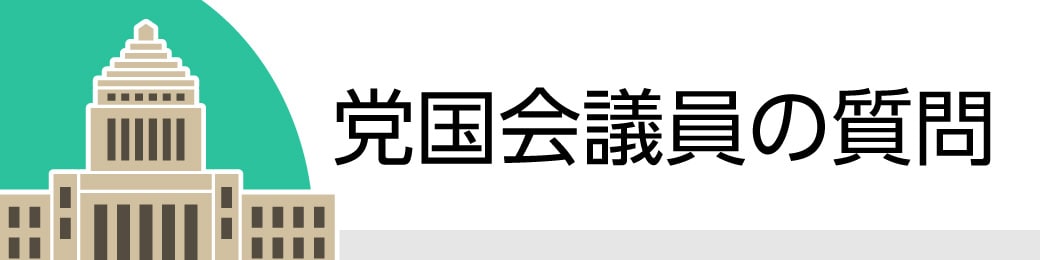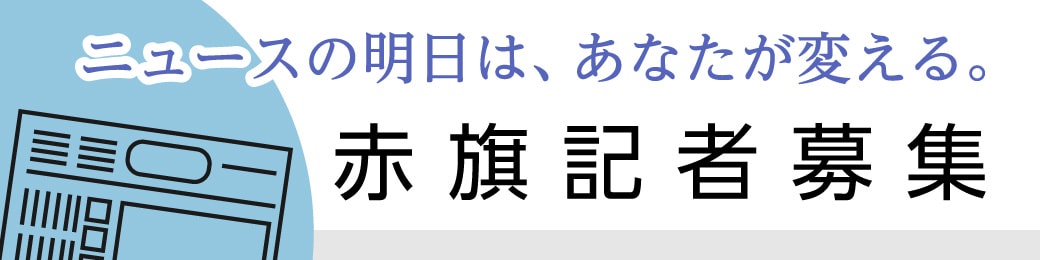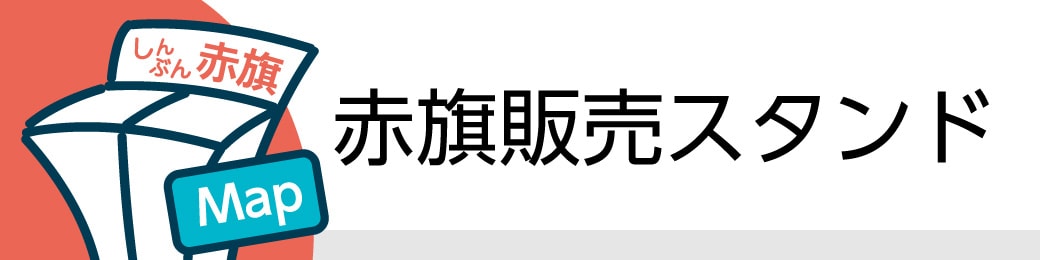2022年12月20日(火)
主張
追い出し違法判決
借り主の居住権侵害許されぬ
賃貸住宅を借りる際、連帯保証人のかわりに家賃滞納時に賃料を保証する「家賃保証会社」と契約するケースが急増しています。それに伴い、保証会社が滞納などを理由に、画一的に借り主を追い出すトラブルが後を絶ちません。家賃を2~3カ月以上滞納すれば契約解除ができたり、住まいを明け渡したとみなしたりできる契約条項などの是非が争われた訴訟で最高裁は12日、これらの契約条項は「消費者である賃借人の利益を一方的に害するもの」だとして、条項の使用差し止めを命じる初めての判決を言い渡しました。
「生活基盤を失わせる」
裁判では、大阪市のNPO法人が大手の保証会社「フォーシーズ」の契約書の明け渡しなどをめぐる条項について、消費者契約法に違反すると訴えていました。
問題の契約条項は、家賃滞納が3カ月以上になった時、保証会社が借り主に知らせないで賃貸借契約を解除できるという内容です。最高裁は、契約を解除できるのは保証会社でなく家主だとした上で、契約解除は借り主の「生活の基盤を失わせる重大な事態を招き得る」と述べ、無通告の契約解除は違法で、無効としました。
家賃2カ月以上を滞納し、連絡がつかずに電気などが長く未使用の場合は明け渡しがあったとみなす、もう一つの契約条項についても最高裁は違法としました。借り主の建物を使う権利が消滅していないのに、保証会社が一方的に権利を制限することになる違法性などを指摘しました。
他の保証会社でも同種の条項があるといいます。全国借地借家人組合連合会(全借連)などは事実上の「追い出し条項」であり、居住権を侵害していると批判してきました。国土交通省によると保証会社は全国に約250社あり、住宅管理会社が保証会社を利用する割合は80%(2021年度)に達します。全借連が9~10月に実施した「家賃保証業者実態調査」(回答142人)では約9割の借り主がやむなく契約したと答えました。ほとんどが保証会社を自分で選べず、契約の説明が不十分な場合も少なくありません。保証会社と契約するのに保証人を求められたとの訴えもありました。
保証会社をめぐっては、家賃滞納を理由に玄関の鍵をロックして室内に入れなくしたり家財道具を全て処分したりして、借り主がホームレス状態になるなどの悪質なケースが相次ぎ、国交省はガイドラインをつくり17年には登録制度を始めた経過があります。
同制度の登録は任意で、罰則の規定もありません。国交省が把握できない業者も多く、野放し状態が続いています。借り主が不利益を受ける現状は早期に正されなければなりません。
規制強化に国は責任持て
最高裁判決により、各保証会社の契約条項の見直しや改定は避けられません。借り主の権利を損なう不当な賃貸借契約の横行を放置してきた国の責任も厳しく問われます。保証会社への規制強化とともに、業態のあり方自体を検討することも必要です。
弱い立場にある借り主の居住権を保障するため、民間会社任せにせず、国が責任を果たさなくてはなりません。公的な家賃保証人制度の創設や家賃補助制度の確立が急がれます。