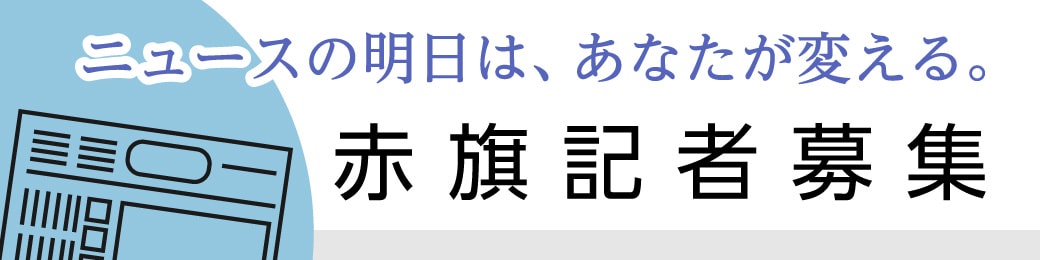2013”N10Œژ11“ْ(‹à)
پuŒأ“T‹³ژ؛پv‘و‚Pٹھ‚ًŒê‚é
ƒ}ƒ‹ƒNƒX‚ً“ا‚ف ‚¢‚ـ‚ةگ¶‚©‚·
ژذ‰ï•دٹvŒˆ‚ك‚éپuڈم•”چ\‘¢پv‚ج“¬‘ˆ
پ@‚Q‚O‚P‚O”N‚P‚QŒژ‚©‚ç–ٌ‚P”N‘±‚¢‚½پuچj—جپEŒأ“TکA‘±‹³ژ؛پv‚ج‚ب‚©‚جپuŒأ“T‹³ژ؛پv‘و‚P‰غپw’ہ‹àپA‰؟ٹi‚¨‚و‚ر—کڈپپxپiƒ}ƒ‹ƒNƒXپj‚ئ‘و‚Q‰غپwŒoچدٹw”ل”»پEڈکŒ¾پxپi“¯پj‚ھ‚Pچû‚ج–{‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پBچu‹`‚ً’S“–‚µ‚½•s”j“NژO‚³‚ٌپi“}ژذ‰ï‰بٹwŒ¤‹†ڈٹڈٹ’·پj‚ئپAگخگىچNچG‚³‚ٌپiگ_Œثڈ—ٹw‰@‘هٹw‹³ژِپjپAژRŒû•x’j‚³‚ٌپi“}ژذ‰ï‰بٹwŒ¤‹†ڈٹ•›ڈٹ’·پj‚ج‚Rگl‚ة–{‚ج–£—ح‚ب‚ا‚ًŒê‚ء‚ؤ‚à‚ç‚¢‚ـ‚µ‚½پB
 پiژتگ^پjگ_Œثڈ—ٹw‰@‘هٹw‹³ژِپ@گخگىچNچG‚³‚ٌ(چ¶)پA“}ژذ‰ï‰بٹwŒ¤‹†ڈٹڈٹ’·پ@•s”j“NژO‚³‚ٌپi’†‰›پjپA“}ژذ‰ï‰بٹwŒ¤‹†ڈٹ•›ڈٹ’·پ@ژRŒû•x’j‚³‚ٌپi‰Eپj |
‘S‘ج‚ج“ء’¥پ@
ƒ}ƒ‹ƒNƒX‚جگ؛‚ھ•·‚±‚¦‚é
پ@پ\چ،‰ٌ‚جپwŒأ“T‹³ژ؛پx‘S‘ج‚ج“ء’¥‚©‚炨کb‚µ‚‚¾‚³‚¢پB
پ@•s”jپ@پuکA‘±‹³ژ؛پv‚حپA“ْ–{‹¤ژY“}چj—ج‚ئ‰بٹw“Iژذ‰ïژه‹`‚ج—ک_‚»‚ج‚à‚ج‚ئ‚ً‚ ‚ي‚¹‚ؤ•×‹‚µ‚و‚¤‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ھ‘ه‚«‚ب“ء’¥‚إپAژuˆتکa•vˆدˆُ’·‚ھ“}چj—جپAژ„‚حƒ}ƒ‹ƒNƒXپAƒGƒ“ƒQƒ‹ƒX‚جŒأ“T‚ًƒeƒLƒXƒg‚ةچu‹`‚ً’S“–‚µ‚ـ‚µ‚½پB“}–{•”‚ج’†‰›‰ïڈê‚ًƒlƒbƒg’تگM‚إ‘Sچ‘‚ة‚آ‚ب‚°‚é‚ئ‚¢‚¤•ûژ®‚إپAگ\‚µچ‚ف‚ح‚Q–œگl‚ً’´‚¦‚ـ‚µ‚½پB
پ@‚»‚جچu‹`‚ً‚Rٹھ‚ة‚ـ‚ئ‚ك‚½‚ي‚¯‚إ¤‚»‚ج‚³‚¢¢‚ـ‚¦‚ھ‚«پv‚ةڈ‘‚«‚ـ‚µ‚½‚ھپA‚ئ‚‚ةژl‚آ‚ج“_‚ًچl‚¦‚ـ‚µ‚½پB
پ@‘و‚P‚حپAƒeƒLƒXƒg‚ج–â‘è‚إ‚·پBƒ}ƒ‹ƒNƒXپEƒGƒ“ƒQƒ‹ƒX‚ج‰بٹw“Iژذ‰ïژه‹`‚ج—ک_‚ج‚ ‚ç‚ـ‚µ‚ً•×‹‚µ‚ؤ‚à‚炨‚¤‚ئ‚ب‚é‚ئپA‚»‚جچ\گ¬•”•ھ‘S•”‚ًچl‚¦‚é•K—v‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB‚¢‚ـ‚ـ‚إƒ}ƒ‹ƒNƒXژه‹`‚جچ\گ¬•”•ھ‚ئ‚¢‚¤‚ئپAگ¢ٹEٹدپi“NٹwپjپAŒoچدٹwپA–¢—ˆژذ‰ïک_پiژذ‰ïژه‹`ک_پj‚جژO‚آ‚ھ‘هژ–‚¾‚ئŒ¾‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½‚ھپAژ„‚ح‚»‚ê‚ةٹv–½ک_‚ً‚‚ي‚¦‚ؤپuژl‚آ‚جچ\گ¬•”•ھپv‚ئ‚µپA‚»‚ج‘S‘ج‚ً‚ي‚©‚ء‚ؤ‚à‚炤‚و‚¤‚ةپAƒeƒLƒXƒg‚ً‘I‚ر‚ـ‚µ‚½پB
پ@‘و‚Q‚حپAچ،“x‚جچuچہ‚حڈ‰•à‚جگl‚à‘½‚¢‚ئژv‚¢پAŒأ“T‚»‚ج‚à‚ج‚ً‚¢‚ء‚µ‚ه‚ة“ا‚ف‚ب‚ھ‚ç‰ًگà‚µ‚ؤ‚¢‚±‚¤‚ئچl‚¦‚ـ‚µ‚½پB
پ@‘و‚R‚حپA‚»‚جŒأ“T‚ھڈ‘‚©‚ꂽ“–ژ‚جگ¢ٹE‚ج—ًژj‚ئپAƒ}ƒ‹ƒNƒXپEƒGƒ“ƒQƒ‹ƒX‚جژv‘z‚ج”“W‚ج—ًژjپA‚±‚ج“ٌ‚آ‚ج–ت‚إ—ًژj‚ج—¬‚ê‚ً‚آ‚©‚ٌ‚إ‚à‚炤‚±‚ئ‚ة—ح‚ً“ü‚ê‚ـ‚µ‚½پBژ„ژ©گgپAڈ‰‚ك‚ؤƒ}ƒ‹ƒNƒX‚ً“ا‚ٌ‚¾ژپA‚»‚±‚ھ‚ي‚©‚ç‚ب‚¢‚إ‹êکJ‚µ‚ـ‚µ‚½‚©‚ç‚ثپB
پ@چإŒم‚ةپAŒأ“T‚ھ“ْ–{‹¤ژY“}چj—ج‚ة‚ا‚¤گ¶‚«‚ؤ‚¢‚é‚©‚إ‚·پB‚±‚ج—ک_‚ًچ،“ْ‚ج“ْ–{‚ئگ¢ٹE‚ةگ¶‚©‚µپAژ„‚½‚؟‚جٹˆ“®‚جژwگj‚ة‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ھچj—ج‚إ‚·‚©‚çپB
 پiژتگ^پjگV“ْ–{ڈo”إژذپE1600‰~پiگإ•تپj |
پ@ژRŒûپ@چ،‰ٌ‚جپwŒأ“T‹³ژ؛پx‚حپA—v‚ًگ¬‚·–½‘è‚â—pŒê‚ً‘S•”ƒ}ƒ‹ƒNƒX‚جŒ¾—t‚إگà–¾‚·‚é—§ڈê‚ھٹر‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ؤپAپuƒ}ƒ‹ƒNƒX‚جگ؛‚ھ•·‚±‚¦‚éپv‚و‚¤‚ة“ا‚ك‚é–ت”’‚³‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پBپuƒ}ƒ‹ƒNƒX‚حڈ‰‚ك‚ؤپv‚جگl‚ًٹـ‚كƒCƒ“ƒ^پ[ƒlƒbƒg’تگM‚ًژg‚ء‚ؤ‚Q–œگ”گçگl‚ئ‚¢‚¤‹K–ح‚إچs‚ء‚½پA‚»‚¤‚¢‚¤گV‚½‚ب•‘‘ن‚إگ¶‚ـ‚ꂽŒأ“TŒ¤‹†‚جˆê‚آ‚جگ¬‰ت‚¾‚ئٹ´‚¶‚ـ‚·پB
پ@•s”jپ@‚¢‚ـگ¢ٹE‚ج‹¤ژY“}‚ج’†‚إƒ}ƒ‹ƒNƒXپEƒGƒ“ƒQƒ‹ƒX‚ً’¼گع“ا‚قپA‚»‚ê‚ً‚¢‚ـ‚ةگ¶‚©‚·‚آ‚à‚è‚إ“ا‚ٌ‚إ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤“}‚ح“ْ–{‹¤ژY“}ˆبٹO‚ة‚ب‚¢‚ج‚إ‚·پBچj—ج‚ئŒأ“T‚ً—¼•û‚آ‚©‚ف‚ب‚ھ‚ç‚جپA‚±‚ꂾ‚¯‚ج‹K–ح‚ج‹³ژ؛‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپA“}‚ج—ًژj‚إ‚àڈ‰‚ك‚ؤ‚ج‚±‚ئ‚إ‚µ‚½پB
پ@گخگىپ@•s”j‚³‚ٌ‚جپwƒ}ƒ‹ƒNƒX‚حگ¶‚«‚ؤ‚¢‚éپx‚حپA—B•¨ک_پAژ‘–{ژه‹`پA–¢—ˆژذ‰ïک_‚جڈ‡‚إ‚ج‰ًگà‚إ‚µ‚½پBچ،‰ٌپAژ‘–{ژه‹`ک_‚ًچإڈ‰‚ة‚µ‚½‘_‚¢‚ح‚ا‚ج‚ ‚½‚è‚ةپH
پ@•s”jپ@‚¢‚ـ‚جژذ‰ï‚ً‚ا‚¤Œ©‚é‚©‚©‚ç“ü‚é‚ج‚ھ‚ي‚©‚è‚â‚·‚¢‚ئژv‚ء‚½‚ٌ‚إ‚·پB‚»‚ê‚إپw’ہ‹àپA‰؟ٹi‚¨‚و‚ر—کڈپپx‚ًچإڈ‰‚جƒeƒLƒXƒg‚ة‚µ‚ـ‚µ‚½پB
‘و‚P‰غپw’ہ‹àپA‰؟ٹi‚¨‚و‚ر—کڈپپx
‰؟’lک_پEچïژوک_‚س‚ـ‚¦’ہ‹à“¬‘ˆ‚جگيڈp’ٌ‹N‚à
پ@پ\‚P‰غ‚جپw’ہ‹àپA‰؟ٹi‚¨‚و‚ر—کڈپپx‚ة“ü‚肽‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB
پ@ژRŒûپ@‚±‚ê‚حپAƒ}ƒ‹ƒNƒX‚ھƒCƒ“ƒ^ƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹‚ج•]‹c‰ï‚إپAŒoچدٹw‚ً’m‚ç‚ب‚¢گl‚إ‚à‚ي‚©‚é‚و‚¤‚ةکb‚ً‘g‚ف—§‚ؤ‚ؤچs‚ء‚½چu‰‰‚إپA•s”j‚³‚ٌ‚حچu‰‰‚ھگ¶‚ـ‚ꂽŒo‰ك‚ًƒCƒ“ƒ^ƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹‚ج‹cژ–ک^‚إ’ا‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ثپB
 پiژتگ^پj•s”j“NژOپEژذ‰ï‰بٹwŒ¤‹†ڈٹڈٹ’· |
پ@•s”jپ@‚P‚X‚W‚Q”N‚ةƒCƒMƒٹƒX‚ةچs‚ء‚½‚ئ‚«پA‚؟‚ه‚¤‚اƒ}ƒ‹ƒNƒX–vŒم‚P‚O‚Oژü”N‚ج‘O”N‚إپAƒeƒŒƒr‚إ‚àƒ}ƒ‹ƒNƒX‚ً‚â‚éپAƒ}ƒ‹ƒNƒX–{‚ھڈo‚é‚ئ‚¢‚¤ژٹْ‚إپA–{‰®‚ضچs‚ء‚½‚炱‚ج‹cژ–ک^‚Uچû‚ھ‚»‚ë‚ء‚ؤ‚ ‚ء‚½پB‚±‚ê‚ح‚ئژv‚ء‚ؤ”ƒ‚ء‚ؤ‚«‚½‚ج‚إ‚·پB
پ@‚±‚ê‚ً“ا‚ق‚ئپAٹeچ‘‚جƒXƒgƒ‰ƒCƒL‚جژx‰‡‚ب‚ا‚ً‹cک_‚µ‚ؤ‚¢‚éچإ’†‚ةپAƒEƒFƒXƒgƒ“‚ئ‚¢‚¤گl‚ھکJ“‘gچ‡–³—pک_‚ًŒ¾‚¤‚ج‚إ‚·پB“¢ک_‚µ‚و‚¤‚ئ‚ب‚ء‚ؤپA‚»‚جŒمپAƒ}ƒ‹ƒNƒX‚ھ‚Q‰ٌ‚ة‚ي‚½‚ء‚ؤ”½ک_‚جچu‹`‚ً‚·‚éپA‚»‚جŒo‰ك‚ھ‘S•”پA‹cژ–ک^‚إ‚ي‚©‚è‚ـ‚·پB‚»‚جژ‚ج•ٌچگ•¶ڈ‘‚ھپw’ہ‹àپA‰؟ٹi‚¨‚و‚ر—کڈپپx‚ب‚ج‚إ‚·پB
پ@‰ïچ‡‚ةڈW‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚éگl‚½‚؟‚حپAŒoچدٹw‚ج’mژ¯‚à‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‚ب‚¢گl‚½‚؟‚خ‚©‚è‚إ‚·پB‚»‚±‚إپAƒ}ƒ‹ƒNƒX‚ھ‚¢‚ـڈ‘‚¢‚ؤ‚¢‚éچإ’†‚جپwژ‘–{ک_پx‚جƒGƒLƒX‚ًکb‚µپA’ہ‹à“¬‘ˆ‚âکJ“‘gچ‡‚جˆس‹`‚ً‚ئ‚«پAکJ“ژزٹK‹‰‚ج–{“–‚ج‰ً•ْ‚ج“¹‚ح‰½‚©‚ـ‚إ‚ي‚©‚点‚é‚ج‚إ‚·‚©‚çپA–{“–‚ة‚ف‚²‚ئ‚بچu‰‰‚إ‚µ‚½پB
پ@ژRŒûپ@—‚”NٹJ‚¢‚½ƒCƒ“ƒ^ƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹چإڈ‰‚ج‘ه‰ïپEƒWƒ…ƒlپ[ƒu‘ه‰ï‚إپAکJ“‘gچ‡‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚جŒˆ’è‚ھچج‘ً‚³‚ê‚ـ‚·‚ھپA‚»‚±‚إ‚حپuکJ“ژزٹK‹‰‚جٹ®‘S‚ب‰ً•ْپv‚ئ‚¢‚¤”C–±‚ـ‚إ‚¤‚½‚ي‚ê‚ـ‚µ‚½‚ثپB
پ@‚±‚جچu‰‰‚حپA‚ئ‚à‚·‚ê‚خŒoچدٹw‚ج“ü–هڈ‘‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إپA‰؟’l‚ئڈè—]‰؟’l‚ج‚ئ‚±‚ëپi‘و‚Uڈحپ`‚P‚Pڈحپj‚ًˆêگ¶Œœ–½‚ة“ا‚ق‚ھپA’ہ‹à“¬‘ˆک_پi‘و‚P‚Qڈحپ`‚P‚Sڈحپj‚ح—¬‚µ“ا‚ق‚±‚ئ‚ة‚ب‚è‚ھ‚؟‚إ‚·‚ھپA‚à‚ئ‚à‚ئپA‚½‚¢‚ض‚ٌژہ‘H“I‚ب‚½‚½‚©‚¢‚ج‰غ‘è‚ة‘خڈˆ‚·‚éچu‰‰‚¾‚ء‚½‚ج‚إ‚·‚ثپB
پ@•s”jپ@‚±‚جچ‘چغ‘gگD‚ج•]‹cˆُ‚حپAƒCƒMƒٹƒX‚إ‚¢‚¤‚ئکJ“‘gچ‡‚جٹ²•”‚إپAŒم‚ة‚ح‚¸‚ء‚ئ‘جگ§ٹٌ‚è‚ة‚ب‚éگl‚½‚؟‚à‘½‚¢‚ج‚إ‚·‚ھپA‚±‚¤‚¢‚¤گl‚½‚؟‚àپAƒCƒ“ƒ^ƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹‚إƒ}ƒ‹ƒNƒX‚ئ‚ئ‚à‚ةٹˆ“®‚·‚é‚ب‚©‚إپAپgژذ‰ïژه‹`‚ھ“–‘R‚¾پh‚ئ‚¢‚¤•ûŒü‚ة•د‚ي‚ء‚ؤ‚ن‚پAƒ}ƒ‹ƒNƒX‚جچu‰‰‚ح‚»‚جˆê‚آ‚ج“]‹@‚ة‚ب‚ء‚½‚ئ‚¢‚¦‚ـ‚·‚ثپB
پ@‚¢‚ـپAŒم”¼•”•ھ‚ح‚ ‚ـ‚è”MگS‚ة“ا‚ـ‚ê‚ب‚©‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤کb‚ھڈo‚ـ‚µ‚½‚ھپA‰؟’lک_‚ًٹî‘b‚ةچïژو‚جژd‘g‚ف‚ًکb‚µ‚½‚ئ‚±‚ë‚إڈI‚ي‚è‚إ‚ح‚ب‚پAƒ}ƒ‹ƒNƒX‚حپA‚»‚±‚©‚ç’ہ‹à“¬‘ˆ‚ح‚¢‚©‚ة•K—v‚©پAکJ“ژز‚حژ‘–{‚ج‚»‚جچïژو‚ة‚½‚¢‚µ‚ؤ‚ا‚¤‚½‚½‚©‚¤‚ׂ«‚©‚ًڈع‚µ‚گà–¾‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚±‚¤‚¢‚¤کb‚حپAپwژ‘–{ک_پx‚ة‚à‚ا‚±‚ة‚àڈo‚ؤ‚¢‚ـ‚¹‚ٌپB‚±‚جچu‰‰‚إ‚µ‚©‚â‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚¢کb‚ب‚ج‚إ‚·پB
پ@گيŒمپA“ْ–{‚إکJ“‘gچ‡‰^“®‚ھ•œٹˆ‚µ‚½‚ئ‚«‚ةپA‚±‚جƒeƒLƒXƒg‚إ•×‹‚µ‚½‘gچ‡ٹ²•”‚ھپAژ‘–{‰ئ‚ئ‚جŒًڈآ‚ة‚»‚ê‚ًژg‚ء‚ؤپu‰؟’l’ت‚è‚ج’ہ‹à‚ً‚و‚±‚¹پv‚ئ‚¢‚ء‚½‚肵‚½‚±‚ئ‚ھ‚و‚‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB
پ@‚µ‚©‚µپAƒ}ƒ‹ƒNƒX‚حپA‚»‚ٌ‚ب‚±‚ئ‚ح‚¢‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ج‚إ‚·‚ثپBƒ}ƒ‹ƒNƒX‚حپAپuکJ“—ح‚ج‰؟’lپv‚حچD‹µ•s‹µ‚ً’ت‚¶‚ؤ‚جکJ’ہ‚ج•½‹د’l‚ب‚ج‚¾‚©‚çپA‚ا‚ٌ‚بŒoچدڈîگ¨‚ج‚à‚ئ‚إ‚àٹو’£‚ء‚ؤ‚½‚½‚©‚ي‚ب‚¯‚ê‚خƒ_ƒپ‚¾پAپuŒi‹C‚ھ‚¢‚¢ژ‚ةپA‚¤‚ٌ‚ئ‚ئ‚ء‚ؤ‚¨‚©‚ب‚¢‚ئپA•s‹µ‚جژ‚ة‘¹‚·‚邼پv‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ب‚اپA”ٌڈي‚ةژہ‘H“I‚بŒ`‚إپA–â‘è‚ً’ٌ‹N‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
 پiژتگ^پjگخگىچNچGپEگ_Œثڈ—ٹw‰@‘هٹw‹³ژِ |
پ@گخگىپ@‚»‚جژي‚ج‹cک_‚حپA‚¢‚ـ‚إ‚à’ہ‹àک_‚ج•ھ–ى‚ة‚¯‚ء‚±‚¤ژc‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ٌ‚إ‚·‚وپB–{—ˆ•¥‚ي‚ê‚é‚ׂ«‚à‚ج‚ھکJ“—ح‚ج‰؟’l‚إ‚ ‚ء‚ؤپAŒ»ژہ‚ھ‚»‚±‚ة’ا‚¢•t‚¢‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚©‚çپA‚»‚±‚ً–„‚ك‚é‚ج‚ھ’ہ‹à“¬‘ˆ‚¾‚ئ‚¢‚¤‹ط—§‚ؤ‚إ‚·‚ثپB
پuژٹش‚حگlٹش‚ج”’B‚جڈêپv–¢—ˆژذ‰ï‚ج•ûŒü‚ًژ¦‚·
پ@ژRŒûپ@Œأ“T‹³ژ؛‚ج’†‚إ‚à”½‹؟‚ھ‘ه‚«‚©‚ء‚½‚ج‚حپAکJ“ژٹش‚ج’Zڈk‚ً‚ك‚®‚ء‚ؤپuژٹش‚حگlٹش‚ج”’B‚جڈꂾپv‚ئ‚¢‚¤‚ئ‚±‚ëپA‚±‚±‚ةپAژ‘–{ژه‹`ژذ‰ï‚ج•دٹv‚ئژذ‰ïژه‹`ژذ‰ï‚جژہŒ»‚ً“W–]‚·‚éˆê‚آ‚جڈd—v‚بŒ´“®—ح‚ھ‚ ‚é‚ئ‚¢‚¤‚ئ‚±‚ë‚إ‚·پB
پ@گخگىپ@“}چj—ج‰ü’è‚جژ‚ة‹cک_‚µ‚½‚ئ‚±‚ë‚إ‚·‚ثپB
پ@•s”jپ@‚±‚ê‚حپAکJ“ژٹش‚ج’Zڈk‚ئپuگlٹش‚ج”’Bپv‚ج–â‘è‚إپAƒ}ƒ‹ƒNƒX‚ھپwژ‘–{ک_پx‚ج‘گچe‚ًژ·•M‚µ‚ب‚ھ‚炸‚ء‚ئ’ا‹†‚µ‘±‚¯‚½’†گS–â‘è‚جˆê‚آ‚إ‚µ‚½پBƒ}ƒ‹ƒNƒX‚حپA‚²‚ڈ‰ٹْ‚ة‚حپAگlٹشگ¶ٹˆ‚©‚猩‚½–¢—ˆژذ‰ï‘œ‚ًپAگlٹش‚ھ•ھ‹ئ‚ة‚µ‚خ‚ç‚ê‚ب‚‚ب‚ء‚ؤپg’©‚حژë‚è‚ً‚µپA’‹‚ح’ق‚èپA—[•û‚ح–q’{‚ً‚µ‚ؤپA–é‚ح“Nٹw‚ة‚س‚¯‚éپh‚ئ‚¢‚ء‚½ƒCƒپپ[ƒW‚إ•`‚¢‚½‚±‚ئ‚à‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پiپwƒhƒCƒcپEƒCƒfƒIƒچƒMپ[پx‚P‚W‚S‚U”NپjپB‚µ‚©‚µپAپwژ‘–{ک_پx‚ج‘گچe‚ًڈ‘‚«ژn‚ك‚½‚T‚O”N‘م‚²‚ë‚©‚ç‚حپAگlٹش‚ھژ©—R‚ة”’B‚إ‚«‚éژذ‰ï‚ئ‚¢‚¤ƒCƒپپ[ƒW‚ھ’†گS‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚«‚ؤپA‚»‚جژ©—R‚ھکJ“ژٹش‚ج’Zڈk‚ة‚و‚ء‚ؤژہŒ»‚³‚ê‚ؤ‚¢‚‚ئ‚¢‚¤“W–]‚ًŒoچدٹw‚ج’†‚إ‚¸‚ء‚ئ’ا‚ء‚ؤ‚ن‚‚ج‚إ‚·پB
پ@‚U‚T”N‚جƒCƒ“ƒ^ƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹‚ج‚±‚جچu‰‰‚إ‚حپAپuژٹش‚حگlٹش‚ج”’B‚جڈꂾپv‚ئ‚¢‚¤–¾‰ُ‚بŒ¾—t‚إپA–¢—ˆژذ‰ï‚ج‘ه‚«‚ب•ûŒü‚ًکJ“ژز‚ةŒü‚©‚ء‚ؤکb‚µ‚½پA‚±‚ê‚ھ‘هژ–‚ب‚ئ‚±‚낾‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB
پ@گخگىپ@ƒ}ƒ‹ƒNƒX‚جŒoچدٹwŒ¤‹†‚حپAƒCƒ“ƒ^ƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹‚إکJ“‰^“®‚جگو“ھ‚ة—§‚ء‚½ٹˆ“®‚ئگط‚ء‚ؤ‚àگط‚ê‚ب‚¢ٹضŒW‚ة‚ ‚éپB‚»‚±‚ھ”ٌڈي‚ة‹³ŒP“I‚إ‚·‚ثپB
ژ‘–{ژه‹`ٹدپAٹv–½ٹد‚ج“]ٹ·‚جژٹْ‚جچu‰‰‚¾‚ء‚½
پ@•s”jپ@ƒ}ƒ‹ƒNƒX‚جٹˆ“®‚©‚ç‚¢‚¤‚ئپA‚P‚W‚S‚W”N‚ةƒˆپ[ƒچƒbƒpٹe’n‚إ‹N‚«‚½ٹv–½“–ژ‚جکJ“ژز‘gگD‚ح‚»‚جŒم‚ف‚ٌ‚ب‚آ‚ش‚ê‚ؤپA‚T‚V”N‚ة‹°چQ‚ھ‚«‚½‚ئ‚«‚ة‚حپA‘gگD‚à‰^“®‚à‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‚ب‚¢ڈَ‘ش‚إ‚µ‚½،‚»‚ê‚إ‚ः}ƒ‹ƒNƒXپAƒGƒ“ƒQƒ‹ƒX‚ح‹°چQ‚ھ‹N‚±‚ê‚خژذ‰ï“IŒƒ“®‚ھ‹N‚«‚ؤ•K‚¸ٹv–½‚ة‚ب‚é‚ئچl‚¦‚ؤ‘ز‚؟چ\‚¦‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ‚·پB‚µ‚©‚µپA‹°چQ‚ح—ˆ‚½‚ھٹv–½‚ح‚ا‚±‚إ‚à‹N‚«‚ب‚©‚ء‚½پB‚±‚ê‚ح‚Qگl‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‘ه‚«‚بŒoŒ±‚إ‚µ‚½پB
پ@‚»‚ج’†‚إٹeچ‘‚جکJ“‰^“®‚ھ‚µ‚¾‚¢‚ة”“W‚µ‚ؤپAƒCƒMƒٹƒX‚ً’†گS‚ةƒCƒ“ƒ^ƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹‚ھ‚إ‚«‚éپBƒ}ƒ‹ƒNƒX‚ح‚»‚±‚ضژQ‰ء‚µ‚ؤپA‚½‚؟‚ـ‚؟‚»‚جژw“±ژز‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚ن‚«‚ـ‚·پB‚±‚جژٹْ‚ھپA‚â‚ح‚èٹv–½ٹد‚ج“]ٹ·‚ھ‹N‚«‚½ژٹْ‚¾‚ئژv‚¢‚ـ‚·پBٹv–½‚حکJ“ژزٹK‹‰‚ھ–³ڈ€”ُ‚ج‚ـ‚ـ‚إژn‚ـ‚é‚ي‚¯‚إ‚ح‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚·‚ثپB
پ@‚à‚¤ˆê‚آپAژ‘–{ژه‹`ٹد‚ج–ت‚إ‚حپA”ق‚حپw‹¤ژY“}گ錾پxپi‚S‚W”Nپj‚ًڈ‘‚¢‚½‚ئ‚«‚©‚çپA‹°چQ‚حژ‘–{ژه‹`‚ھچإŒم‚ج‹ا–ت‚ة‚«‚½‚±‚ئ‚ج‚ ‚ç‚ي‚ꂾ‚ئŒ©‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پB—کڈپ—¦’ل‰؛‚ج–@‘¥‚ج‰بٹw“I‚بچھ‹’‚ًŒ©‚آ‚¯‚½‚ئ‚«پAƒ}ƒ‹ƒNƒX‚ح‚»‚ج–@‘¥‚ج’†‚ة‹°چQ‚ھ‹N‚«‚éچھŒ¹‚ًŒ©‚ؤپA‚P‰ٌ‚ج‹°چQ‚إٹv–½‚ھژ¸”s‚µ‚ؤ‚àپAژں‚ة‚ح‚à‚ء‚ئ‚ذ‚ا‚¢‹°چQ‚ھ‚«‚ؤژذ‰ï‚ح•دٹv‚ة‚ق‚©‚¤‚ئ‚¢‚¤—ک_‚¾‚ؤ‚ً‚µ‚ـ‚µ‚½پB
پ@‚ئ‚±‚ë‚ھپA‚U‚T”NپA‚±‚جچu‰‰‚ً‚â‚éڈ‚µ‘O‚ةپAپwژ‘–{ک_پx‚ج‘و‚Q•”‚جچإڈ‰‚ج‘گچe‚ًڈ‘‚¢‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚«‚ةپA‹°چQ‚ج‹N‚±‚è•û‚ھ‚»‚¤‚إ‚ح‚ب‚¢‚±‚ئ‚ً”Œ©‚µ‚ـ‚µ‚½پB‹°چQ‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حژ‘–{‚ھڈzٹآ“I‚ة”“W‚µ‚ؤ‚¢‚ˆê‹ا–ت‚إ‚ ‚èپA‚P‰ٌ‚²‚ئ‚ةژ‘–{ژه‹`‚جٹë‹@‚ًگ[‚ك‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚پA‘O‚و‚è‚àچ‚‚¢‚ئ‚±‚ë‚إŒoچد“I”“W‚ھ‚·‚·‚قگV‚µ‚¢ڈzٹآ‚جڈo”“_‚ة‚ب‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ً‚آ‚©‚ق‚ج‚إ‚·،‚؟‚ه‚¤‚ا¤‚»‚جچ ‚حƒˆپ[ƒچƒbƒp‚جژ‘–{ژه‹`‚ھ‘ه”“W‚ةŒü‚©‚¢ڈo‚µ‚½ژ‘م‚إ‚µ‚½‚©‚çپA‚±‚جگV‚µ‚¢Œ©•û‚حŒoچد”“W‚جŒ»ژہ‚ة‚ ‚¤‚ج‚إ‚µ‚½پB
پ@‚±‚جŒ©•û‚ج“]ٹ·‚حپA‚±‚جچu‰‰‚ة‚ح‚ء‚«‚èڈo‚ؤ‚¢‚ـ‚·،‚»‚±‚إ‚ح¤‹°چQ‚ھ•دٹv‚ج“]ٹ·“_‚¾‚ئ‚¢‚¤Œ¾—t‚حˆêگط‚ب‚‚ؤپA‹°چQ‚ج‚ئ‚«‚ةکJ“ژز‚ھ’ہ‹à“¬‘ˆ‚ً‚ا‚¤‚â‚é‚©‚ھ–â‘肾‚ئ‚¢‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‘جگ§•دٹv‚ج‰^“®‚حپA‚»‚¤‚¢‚¤“¬‘ˆ‚ًگد‚فڈd‚ث‚é‚ب‚©‚إ‚جکJ“ژز‚جژ©ٹo‚ج”“W‚ًٹî‘b‚ة‚µ‚ؤ”“W‚·‚é‚ئ‚¢‚¤ک_—‚à‘g‚ف—§‚ؤ‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@‹°چQک_‚جژd‘g‚ف‚ً”Œ©‚µ‚½‚ئ‚±‚ë‚إپAژ‘–{ژه‹`‚جŒ©•û‚àپAٹv–½‚جŒ©•û‚à•د‚ي‚ء‚½‚ي‚¯‚إپA‚»‚ê‚ھچu‰‰‚ة‹ï‘ج“I‚ةژ¦‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پB‚±‚ê‚ھŒoچدٹw‚ة‚ـ‚ئ‚ـ‚é‚ج‚حپA‚à‚¤‚؟‚ه‚ء‚ئŒمپAپwژ‘–{ک_پx‘و‚P•”پi‚U‚V”Nپj‚ج‚ب‚©‚إ‚إ‚µ‚½پB
پ@‚»‚¤‚¢‚¤ˆس–،‚إپAƒ}ƒ‹ƒNƒX‚ج—ک_‚ج”“W‚ج’†‚إ‚àپA‚½‚¢‚ض‚ٌ‘هژ–‚بˆت’u‚ًگè‚ك‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ً’ةٹ´‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
 پiژتگ^پjژRŒû•x’jپEژذ‰ï‰بٹwŒ¤‹†ڈٹ•›ڈٹ’· |
پ@ژRŒûپ@ٹK‹‰“¬‘ˆک_‚ھژ²‚ة‚ ‚ء‚ؤ—ک_‚ج”“W‚ھچs‚ي‚ê‚é‚ئ‚¢‚¤ˆê‚آ‚ج‚ ‚ç‚ي‚ꂾ‚ئژv‚¢‚ـ‚·‚ثپB
“ْ–{‚جˆظڈي‚ب’ل’ہ‹à‚ًˆê‘|‚µ”²–{“I‚ةˆّ‚«ڈم‚°‚铬‘ˆ‚ً
پ@ژRŒûپ@ƒ}ƒ‹ƒNƒX‚ھƒCƒMƒٹƒX‚ج‚P‚OژٹشکJ“–@پiچHڈê–@پj‚ًپuژذ‰ï“IƒoƒٹƒPپ[ƒhپv‚ئˆس‹`‚أ‚¯‚½‚±‚ئ‚ة‚آ‚¢‚ؤپA‘و‚P‰غ‚جچإŒم‚ةپu•âک_پv‚ئپu•â’چپv‚ھ‚ ‚ء‚ؤپA‚ؤ‚¢‚ث‚¢‚ةگà–¾‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@گخگىپ@ٹwڈK‰ï‚إ‚حپu‚±‚ٌ‚بڈژq‰»‚ً‘±‚¯‚½‚çژذ‰ï‚ھ‰َ‚ê‚é‚ج‚ح‚ي‚©‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ةپA‚ب‚؛چàٹE‚ح‚»‚ٌ‚ب‚±‚ئ‚ً‚·‚é‚ج‚©پv‚ئ‚¢‚¤ژ؟–â‚ً‚و‚•·‚«‚ـ‚·پBŒ‹‹اپA‚±‚ê‚حژ‘–{‚ةٹْ‘ز‚µ‚ؤ‚à–³—‚ب‚±‚ئ‚إپAکJ“ژز‚âژs–¯‚ج‚½‚½‚©‚¢‚ة‚و‚茒‘S‚ب”“W‚ج‹O“¹‚ً‚آ‚‚邵‚©‚ب‚¢پBژ‘–{‚جک_—‚ًکJ“ژز‚ج‘¤‚ھگ§Œن‚·‚é—ح‚ًژ‚½‚ب‚¢‚ئƒ_ƒپ‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚·‚ثپB
پ@•s”jپ@‚»‚¤‚إ‚·‚ثپBƒ}ƒ‹ƒNƒX‚حپwژ‘–{ک_پx‚إپAچHڈê–@‚حکJ“ژز‚ھژ‘–{‰ئ‚ً‹Kگ§‚·‚郋پ[ƒ‹‚ً‚©‚؟‚ئ‚ء‚½‚à‚ج‚¾پA‚ئ‚¢‚¤ˆس–،‚ج‚±‚ئ‚ًŒJ‚è•ش‚µŒ¾‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBژہچغ¤ƒCƒMƒٹƒX‚إ‚औ¼گ¢‹I‚ة‚ي‚½‚éکJ“ژز‚ج“¬‘ˆ‚ھپAچ‘‚ً“®‚©‚µ‚ؤ–@—¥‚إژ‘–{‰ئ‚ةکJ“ژٹش’Zڈk‚ً‹گ§‚µ‚½‚ج‚إ‚·‚©‚çپBپuژذ‰ï“IƒoƒٹƒPپ[ƒhپv‚ئ‚¢‚¤Œ¾—t‚à‚»‚ج‚ب‚©‚إڈo‚ؤ‚«‚½‚à‚ج‚إ‚µ‚½پB
پ@گخگىپ@’ہ‹à‚ً‚ك‚®‚ء‚ؤ‚حپA“ْ–{‚ج”ٌگ³‹KکJ“ژز‚ھژ©•ھ‚ئ‰ئ‘°‚جکJ“—ح‚جچؤگ¶ژY”ï‚·‚çژَ‚¯ژو‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ھپAƒ}ƒ‹ƒNƒX‚ض‚ج‹^–â‚ئ‚µ‚ؤکb‘è‚ة‚ب‚邱‚ئ‚à‚ ‚è‚ـ‚·پB
پ@ژRŒûپ@کJ“—ح‚ج‰؟’l‚ة‚حپAچإ’لŒہ‚جگ¶ٹˆ‚ة•K—v‚ب‚à‚ج‚ئ‚¢‚¤—v‘f‚ئپAژذ‰ï“IپE•¶‰»“I—v‘f‚ج“ٌ‚آ‚ھ‚ ‚èپA•¶‰»“I—v‘f‚ح“¬‘ˆ‚إ‚µ‚©Œˆ‚ـ‚ç‚ب‚¢پA‚ئƒ}ƒ‹ƒNƒX‚حŒ¾‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ثپB
پ@گخگىپ@‚ ‚ي‚¹‚ؤ‚±‚ج‚ ‚½‚è‚جƒ}ƒ‹ƒNƒX‚ج‹cک_‚إ‚حپAپuکJ“—ح‚ج‰؟’lپv‚àژذ‰ï“IپE•½‹د“I‚ةŒv‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ً‰ں‚³‚¦‚é•K—v‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚ثپB
پ@•s”jپ@“ْ–{‚ج‚¢‚ـ‚ج”hŒکJ“ژز‚ب‚ا‚حپAچإ’لگ¶ٹˆ‚³‚¦ٹ„‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ي‚¯‚إ‚·پB‚±‚¤‚¢‚¤ڈَ‘ش‚ھ‰½ڈ\”N‚à‘±‚«پA‚ـ‚½چL‚ھ‚é‚ئپA‚±‚ê‚ھ“ْ–{‚جکJ“ژز‚ج“–‚½‚è‘O‚ج—ًژj“Iگ¶ٹˆڈَ‘ش‚¾‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚ء‚ؤپAکJ“—ح‚ج‰؟’l‚»‚ج‚à‚ج‚ة‹؟‚¢‚ؤ‚‚éٹ댯‚³‚¦ٹ´‚¶‚ـ‚·پB‚±‚ٌ‚بˆظڈي‚بڈَ‘ش‚ًˆê‘|‚µ‚ؤپA’ہ‹à‚ً”²–{“I‚ةˆّ‚«ڈم‚°‚铬‘ˆ‚ًپAکJ“‘gچ‡‚¾‚¯‚ج–â‘è‚ة‚ئ‚ا‚ك‚¸پA“ْ–{‚جکJ“ژزٹK‹‰‚ج’ہ‹àگ…ڈ€پA‚¢‚ي‚خچ‘–¯“I‚بگ¶ٹˆگ…ڈ€‚ًŒˆ‚ك‚铬‘ˆ‚ئ‚¢‚¤ٹoŒه‚إ‚½‚½‚©‚ي‚ب‚¯‚ê‚خ‚¢‚¯‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚·پB
پ@گخگىپ@گإ‹àپAچ‘‰ئ—\ژZ‚جŒ¹گٍ‚ھڈè—]‰؟’l‚¾‚ئ‚¢‚¤‚ئ‚±‚ë‚àڈd—v‚إ‚·‚ثپB‚»‚¤‚µ‚ؤ‹z‚¢ڈم‚°‚ç‚ꂽ—\ژZ‚ًپA‚½‚½‚©‚¢‚ج—ح‚إژذ‰ï•غڈل‚âˆم—أ‚ب‚ا‚ةژg‚ي‚¹‚ؤ‚¢‚‚±‚ئ‚حپAکJ“—ح‚جچؤگ¶ژY”ï‚ئ‚µ‚ؤ‚±‚ê‚ًژو‚è•ش‚µ‚ؤ‚¢‚ˆس–،‚ً‚à‚آ‚ي‚¯‚إ‚·پB
‘و‚Q‰غپwŒoچدٹw”ل”»پEڈکŒ¾پx
ƒ}ƒ‹ƒNƒX‚جژ©Œبڈذ‰î‚ً‚ا‚¤“ا‚ق‚©
پ@پ\‚إ‚حپA‘و‚Q‰غ‚ة‚ح‚¢‚è‚ـ‚µ‚ه‚¤پB
پ@ژRŒûپ@‘و‚Q‰غ‚إ‚حپwŒoچدٹw”ل”»پEڈکŒ¾پxپi‚P‚W‚T‚X”Nپj‚ًژو‚èڈم‚°‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚±‚±‚إƒ}ƒ‹ƒNƒX‚حژj“I—B•¨ک_‚ة‚آ‚¢‚ؤŒn““I‚ةگà–¾‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚·‚ثپB
پ@•s”jپ@‚±‚±‚إڈq‚ׂç‚ê‚ؤ‚¢‚éژj“I—B•¨ک_‚جƒ}ƒ‹ƒNƒX‚جƒeپ[ƒ[‚ةپuٹK‹‰پv‚ھ‚إ‚ؤ‚±‚ب‚¢‚±‚ئ‚ھپAژہ‚حپAگج‚©‚ç”Y‚ـ‚µ‚©‚ء‚½‚ج‚إ‚·پBپw‹¤ژY“}گ錾پxپi‚S‚W”Nپj‚إ‚حپAپuژذ‰ï‚ج—ًژj‚حٹK‹‰“¬‘ˆ‚ج—ًژj‚¾پv‚ئ‚¢‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ةپB
پ@ƒ}ƒ‹ƒNƒX‚حژèژ†‚إ‚àڈ‘‚¢‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚·‚ھپA•غژçگF‚ج‹‚¢ƒhƒCƒc‚جŒoچدٹwٹE‚ةچإڈ‰‚جŒoچدٹw“IکJچى‚ً‚à‚ء‚ؤ“oڈê‚·‚é‚ة‚ ‚½‚ء‚ؤپAچإڈ‰‚©‚çگFٹل‹¾‚إŒ©‚ç‚ê‚ؤ–³ژ‹‚³‚ê‚ب‚¢‚و‚¤‚ةپAژj“I—B•¨ک_‚ج’èژ®‚ة‚ ‚½‚ء‚ؤ‚àپA’چˆسگ[‚¢چH•v‚ً‚µ‚½‚ج‚إ‚·‚ثپB‚¾‚©‚çپAپuٹK‹‰پv‚ئ‚©پuچïژوپvپuژذ‰ïژه‹`پv‚ب‚ا‚جŒ¾—t‚حژg‚ي‚ب‚¢‚إ’†گg‚ً•\Œ»‚µ‚½‚ج‚¾‚ئچl‚¦‚ؤپA‚و‚¤‚â‚نDپi‚سپj‚ة‚¨‚؟‚ـ‚µ‚½پB
پ@ژRŒûپ@‚»‚±‚إپwŒأ“T‹³ژ؛پx‚إ‚حپAŒoچدٹw”ل”»‚جڈکŒ¾‚إ‚جƒ}ƒ‹ƒNƒX‚جژ©Œبڈذ‰î‚ًپAٹv–½‰ئ‚ئ‚µ‚ؤ‚جƒ}ƒ‹ƒNƒX‚جٹˆ“®—ً‚ً•â‚¢‚ب‚ھ‚ç“ا‚ٌ‚¾‚ي‚¯‚إ‚·‚ثپB
پ@گخگىپ@‘¼•û‚إپw‹¤ژY“}گ錾پx‚جژ·•Mژز‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ًپAƒ}ƒ‹ƒNƒX‚ھ‚ ‚炽‚ك‚ؤٹm”F‚µ‚ؤ‚¢‚镶ڈح‚ب‚ا‚à‚ ‚è‚ـ‚·‚ثپB
پ@•s”jپ@–ت”’‚¢‚ئژv‚ء‚½‚ج‚حپAƒGƒ“ƒQƒ‹ƒX‚ئƒ}ƒ‹ƒNƒX‚جڈo‰ï‚¢‚إ‚·پBƒGƒ“ƒQƒ‹ƒX‚àپAƒwپ[ƒQƒ‹“Nٹw‚جگM•ٍژز‚ئ‚¢‚¤“¯‚¶‚ئ‚±‚ë‚©‚çڈo”‚·‚é‚ج‚إ‚·‚ھپAƒCƒMƒٹƒX‚إژ‘–{ژه‹`‚جŒ»ژہ‚ئکJ“ژزٹK‹‰‚ج“¬‘ˆ‚جژہچغ‚ة‚س‚ê‚ؤژذ‰ïژه‹`‚ة“ü‚é‚ج‚إ‚·پBƒ}ƒ‹ƒNƒX‚ج•û‚حپAƒwپ[ƒQƒ‹‚ج–@“Nٹw‚جژذ‰ïٹد‚ً“ھ‚ة‚½‚½‚«‚±‚ٌ‚إپAƒ‰ƒCƒ“گV•·‚ج•زڈW’·‚ة‚ب‚ء‚ؤپA‚»‚±‚إŒoچدŒ»ڈغ‚ة‚ش‚آ‚©‚èپAƒwپ[ƒQƒ‹‚ج’mژ¯‚إ‚ح‘«‚è‚ب‚¢‚ئƒwپ[ƒQƒ‹‚ج–@“Nٹw‚ً“ا‚ف’¼‚·‚ج‚إ‚·پBپwƒwپ[ƒQƒ‹چ‘–@ک_”ل”»پx‚ة‚حپAƒ}ƒ‹ƒNƒX‚ج‘جŒ±‚ة‚½‚ء‚½ژذ‰ïک_‚ئƒwپ[ƒQƒ‹‚جژذ‰ïک_‚ھ‚ش‚آ‚©‚ء‚ؤپAژذ‰ïٹد‚ھ‚ذ‚ء‚‚è•ش‚ء‚ؤ‚¢‚—lژq‚ھ‚و‚‚إ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@‚¾‚©‚çƒ}ƒ‹ƒNƒX‚ھژj“I—B•¨ک_‚ة“’B‚µ‚½‚ئ‚«‚ة‚حپAژذ‰ï‚ً‚ئ‚炦‚éڈ”ٹT”O‚ھ‘ٹ“–گ®—‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپBƒGƒ“ƒQƒ‹ƒX‚حƒCƒMƒٹƒXژ‘–{ژه‹`‚ً‚و‚’m‚ء‚ؤ‚¢‚邵پAƒvƒچƒŒƒ^ƒٹƒAپ[ƒg‚ج‰^“®‰ئ‚ئ‚جŒً—¬‚à‚ ‚éپB‚»‚¤‚¢‚¤‚Qگl‚جچ‡چى‚إژj“I—B•¨ک_‚ھ‚إ‚«‚ ‚ھ‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپA‚½‚¢‚ض‚ٌ‚¤‚ـ‚¢—ًژj“I‘ک‹ِ‚¾‚ء‚½‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB
ژj“I—B•¨ک_‚حگي‘O‚ج“ْ–{ژذ‰ï‚إ‚ا‚ٌ‚ب–ًٹ„‚ً‰ت‚½‚µ‚½‚©
پ@ژRŒûپ@‘و‚Q‰غ‚إ‚حپAƒ}ƒ‹ƒNƒX‚جژ©Œبڈذ‰î‚ة‚آ‚أ‚¢‚ؤپAژj“I—B•¨ک_‚ھ“ْ–{‚جژذ‰ï‚إ‚ا‚ٌ‚ب–ًٹ„‚ً‰ت‚½‚µ‚½‚©‚ًŒ©‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚»‚ج’†‚إپAگي‘O‚ج“ْ–{‚جژx”z“I‚ب—ًژjٹد‚ئ‚µ‚ؤپuŒRگl’؛—@پv‚ة’چ–ع‚µ‚½‚ج‚حڈd—v‚إ‚·‚ثپB
پ@•s”jپ@‚±‚ج“_‚إ‚ح‚و‚¢‹³ˆç’؛Œê£‚ھ–â‘è‚ة‚ب‚é‚ج‚إ‚·‚ھپA¢‹³ˆç’؛Œê£‚ة‚ح“Vچcگ§‚ج—ًژj‚حˆêŒ¾‚µ‚©ڈ‘‚¢‚ؤ‚ب‚¢‚ج‚إ‚·،‚ئ‚±‚ë‚ھ¤¢ŒRگl’؛—@£‚ح“Vچc’†گS‚جŒ©•û‚إ“ْ–{‚ج—ًژj‚ھ‚¸‚ء‚ئڈ‘‚¢‚ؤ‚ ‚èپAŒR‘à‚¾‚¯‚إ‚ب‚’†ٹwچZ‚©‚ç‚»‚ê‚ً‚½‚½‚«چ‚ـ‚êپA‚»‚ê‚إ—ًژj‚ًٹo‚¦‚½‚ج‚إ‚·پB‚¾‚©‚çپAژ„‚حپA‚±‚ê‚ھگي‘O‚ج“ْ–{‚جچ‘–¯“I‚ب—ًژjٹد‚جٹî–{‚ة‚ب‚ء‚½‚±‚ئ‚حٹشˆل‚¢‚ب‚¢‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@ژRŒûپ@“Vچcگâ‘خ‚ج—ًژjٹد‚ھژx”z“I‚¾‚ء‚½‚»‚¤‚¢‚¤ژٹْ‚ةپA–ىکC‰h‘¾کY‚½‚؟‚جژj“I—B•¨ک_‚ة‚و‚éژ©ژه“I‚ب“ْ–{—ًژj‚جŒ¤‹†‚ھژn‚ـ‚ء‚½پB‚»‚جˆس‹`‚ھ‘خ”ن‚µ‚ؤ‚و‚‚ي‚©‚é‚ئژv‚¢‚ـ‚·‚ثپB
پ@•s”jپ@“ْ–{‚جگي‘O‚جƒ}ƒ‹ƒNƒXژه‹`Œ¤‹†‚حپAƒXƒ^پ[ƒٹƒ“ˆب‘O‚جچ‘چغ“I‚بƒ}ƒ‹ƒNƒXژه‹`Œ¤‹†‚ً‹zژû‚µ‚ب‚ھ‚çپAژ©ژه“I‚ة”“W‚µ‚½‚ج‚إ‚·پB
پ@“ْ–{‚جƒ}ƒ‹ƒNƒXژه‹`ژز‚ھ“ئژ©‚ة“ْ–{ژذ‰ï‚ًŒ¤‹†‚µ‚ؤˆّ‚«‚¾‚µ‚½“ْ–{ژذ‰ï•دٹv‚ج•ûگj‚ھپAŒم‚©‚çڈo‚½ƒRƒ~ƒ“ƒeƒ‹ƒ“‚جƒeپ[ƒ[پi‚P‚X‚Q‚V”NپA‚R‚Q”Nپj‚ئˆê’v‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚حپAˆس‹`‚ ‚é—ًژj‚¾‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB
“y‘ن‚ئڈم•”چ\‘¢‚ج‘ٹŒفچى—p‚إژذ‰ï•دٹv‚ً‚ئ‚炦‚é
پ@ژRŒûپ@ژj“I—B•¨ک_‚جکZ‚آ‚جƒeپ[ƒ[‚ج‚ئ‚±‚ë‚إ‚حپAژذ‰ï•دٹv‚ج‰^“®‚جˆت’u‚ئ–ًٹ„‚ھ•‚‚«’¤‚è‚ة‚ب‚ء‚½‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB
پ@گخگىپ@“ٌ‚آ–ع‚جƒeپ[ƒ[‚ة‚©‚©‚ي‚ء‚ؤپA“y‘ن‚ھڈم•”چ\‘¢‚ًپu‹K’è‚·‚éپv‚ئ‚¾‚¯•\Œ»‚·‚é‚ئپAŒoچدŒˆ’èک_‚¾‚ئ‚¢‚¤Œë‰ً‚ً“±‚«‚â‚·‚¢‚ئ‚±‚ë‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚ثپB‚»‚±‚حƒGƒ“ƒQƒ‹ƒX‚ھ”س”N‚جژèژ†‚إŒê‚ء‚½پA•s“™‚ب—ح‚جپu‘ٹŒفچى—pپv‚ئ‚¢‚¤•\Œ»‚إ•â‚¤‚±‚ئ‚ھ•K—v‚¾‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@•s”jپ@چu‹`‚إ‚حپAکZ‚آ‚جƒeپ[ƒ[‚ة•ھ‚¯‚ؤگà–¾‚µ‚ـ‚µ‚½‚ھپAƒ}ƒ‹ƒNƒXژ©گg‚حپAژj“I—B•¨ک_‚ج’èژ®‘S‘ج‚ً‚ـ‚ء‚½‚چs‚ً•د‚¦‚ب‚¢‚إپAچإڈ‰‚©‚çچإŒم‚ـ‚إˆê‘±‚«‚ج•¶ڈح‚ئ‚µ‚ؤڈ‘‚¢‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚±‚ê‚حˆس–،‚ھ‚ ‚é‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB”ق‚ھ‚±‚±‚إˆê”شŒ¾‚¢‚½‚©‚ء‚½‚ج‚حپAژذ‰ï•دٹv‚ح‚ا‚¤‚¢‚¤—ح‚ة‚و‚ء‚ؤگ¶‚ـ‚êپA‚ا‚¤‚¢‚¤‰ك’ِ‚إژہŒ»‚·‚é‚©پA‚ئ‚¢‚¤–â‘肾‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB
پ@Œoچد“I“y‘ن‚ة‚¨‚¢‚ؤگ¶ژY—ح‚ئگ¶ژYٹضŒW‚ج–µڈ‚‚ھ”“W‚µ‚ؤپAگ¶ژYٹضŒW‚ھگ¶ژY—ح‚جپu~‡پi‚µ‚ء‚±‚پjپvپi’چپj‚ة‚ب‚ء‚½‚ئ‚«‚ةژذ‰ïٹv–½‚جژ‘م‚ھژn‚ـ‚éپA‚±‚ê‚ح“y‘ن‚ج–â‘è‚إ‚·‚ثپB‚إ‚حپAژذ‰ïٹv–½‚ح‚ا‚±‚إŒˆ’…‚ھ‚آ‚‚©‚ئ‚¢‚¦‚خپAڈم•”چ\‘¢‚إŒˆ’…‚ھ‚آ‚پB‚±‚ê‚حپAژذ‰ï‚ج•دٹv‚إ‚حڈم•”چ\‘¢‚ھژه—v‚ب–ًٹ„‚ً‚ة‚ب‚¤پA‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚·پB
پ@پi’چپj~‡پ@ژè‚©‚¹‘«‚©‚¹‚ج‚±‚ئپBپwژ‘–{ک_پx‚ة‚àڈo‚ؤ‚«‚ـ‚·‚ھپAƒ}ƒ‹ƒNƒX‚حپAگ¶ژY—ح‚ئگ¶ژYٹضŒW‚ھ–µڈ‚‚ةٹׂ邱‚ئ‚ًپA‚±‚جŒ¾—t‚إ•\Œ»‚µ‚ـ‚µ‚½پB
پ@‚»‚ج‚¤‚¦‚إپA‚à‚¤ˆê“xپAپuژذ‰ïچ\گ¬‘ج‚حپA‚·‚ׂؤ‚جگ¶ژY—ح‚ھ”“W‚µ‚«‚ç‚ب‚¢‚¤‚؟‚ح‚¯‚ء‚µ‚ؤ–v—ژ‚µ‚ب‚¢پv‚ئ•دٹv‚ئ“y‘ن‚جٹضŒW‚ة–ك‚è‚ـ‚·‚ھپA‚±‚±‚إژw“E‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚حپA•دٹv‚ھ–â‘è‚ة‚ب‚é‚ج‚حپAŒoچد“I“y‘ن‚ة‚±‚ꂾ‚¯‚ج•دٹv‚ھگ¶‚ـ‚ê‚é‚ئ‚«‚¾‚ئ‚¢‚¤•¨ژ؟“Iڈ”ڈًŒڈ‚إ‚ ‚ء‚ؤپA‚»‚جڈًŒڈ‚ًٹˆ—p‚µ‚ؤŒ»ژہ‚ةژذ‰ï•دٹv‚ھژہŒ»‚·‚é‚©‚ا‚¤‚©‚حپAگlٹش‚جٹˆ“®پA‚آ‚ـ‚èڈم•”چ\‘¢‚إ‚جڈ”“¬‘ˆ‚ة‚و‚ء‚ؤŒˆ‚ـ‚é‚ج‚إ‚·پBŒoچدڈًŒڈ‚إ‚ج–µڈ‚‚جگ¬ڈn‚حٹv–½‚ج•K—vڈًŒڈ‚إ‚ ‚ء‚ؤپAڈ\•ھڈًŒڈ‚إ‚ح‚ب‚¢پB‚±‚±‚إ‚حپAٹv–½ک_‚ًژ²‚ة‚µ‚ؤپAŒoچدŒˆ’èک_‚ة‚ح‚ب‚è‚و‚¤‚ج‚ب‚¢–¾ٹm‚بڈ‘‚«•û‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚·‚ثپB
پ@گخگىپ@ژ‘–{ژه‹`‚ھ”“W‚·‚é‚ظ‚اڈم•”چ\‘¢‚ھ‹گ‘ه‚ة‚ب‚èپAژx”zٹK‹‰‚ھچ‘–¯‘½گ”‚ًژ©•ھ‚ة‚ذ‚«‚آ‚¯‚و‚¤‚ئ‚·‚é‚ئ‚¢‚¤•s”j‚³‚ٌ‚جژw“E‚حپAŒ»‘م‚جژذ‰ï‚ًŒ©‚邤‚¦‚إڈd—v‚إ‚·‚ثپBچàٹE‚à‘I‹“‚إ‘½گ”‚ًٹl“¾‚µ‚ب‚¢‚ئژx”z‚ھگ¬‚è—§‚½‚ب‚¢‚ي‚¯‚إپAƒپƒfƒBƒA‚ئ‹³ˆç‚ً‚آ‚©‚ء‚ؤچ‘–¯‘½گ”‚ً‚ ‚éژيپAگô”]‚¹‚ث‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢پB‚»‚ج‚½‚ك‚ةƒپƒfƒBƒA‚ب‚ا‚ً‹گ‘ه‰»‚³‚¹‚ؤ‚¢‚‚ي‚¯‚إ‚·‚ثپB
پ@•s”jپ@ƒ}ƒ‹ƒNƒX‚حچإڈ‰پAƒCƒMƒٹƒX‚إکJ“ژز‚ھ‘I‹“Œ ‚ً“¾‚ê‚خکJ“ژز‚جŒ —ح‚ھ‚إ‚«‚é‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ي‚¯‚إ‚·پB‚µ‚©‚µپA‘I‹“گ§“x‚ج‰üٹv‚ھگi‚فکJ“ژز‚ھ‚ف‚ٌ‚ب‘I‹“Œ ‚ًژ‚آ‚و‚¤‚ة‚ب‚é‚ئپAژ‘–{‰ئ‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚¢‚©‚ةکJ“ژز‚ً‚آ‚©‚ق‚©‚ھ‘هژ–‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚‚éپB
پ@ƒ}ƒ‹ƒNƒX‚جژ‘م‚حپAژ‘–{‰ئٹK‹‰‚ھ‘gگD‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚¹‚ٌپB‚»‚ê‚ة”ن‚×پA‚¢‚ـ‚ج“ْ–{‚ج‘هٹé‹ئپEچàٹE‚حکJ“ژز‚و‚è‚ح‚é‚©‚ة‘gگD‚³‚êپAٹK‹‰“Iˆسژ¯‚ً‚à‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚وپBکJ“ژزٹK‹‰‚ج—}‚¦•û‚àƒ}ƒ‹ƒNƒXˆبŒم‚ة”“W‚µ‚ؤ‚¢‚پB‚¾‚©‚çژ‘–{ژه‹`‚ھ”’B‚·‚é‚ةڈ]‚ء‚ؤپAڈم•”چ\‘¢‚إŒˆ’…‚·‚éژdژ–‚ھ‘ه‹K–ح‚ة‚ب‚é‚ٌ‚إ‚·‚ثپB
پ@گخگىپ@گ¶ژYٹضŒW‚ھگ¶ژY—ح”“W‚جپu~‡پv‚ة‚ب‚é‚ئ‚¢‚¤‘و‚R‚جƒeپ[ƒ[‚ج‰ًگà‚إپAŒ»‘م‚ج~‡‚ئ‚µ‚ؤ’n‹…‰·’g‰»‚⌴”‚ج–â‘è‚ً‚ ‚°‚ç‚ê‚ؤ‚ـ‚·‚ھپB
پ@•s”jپ@‚ا‚؟‚ç‚àپA‚ـ‚³‚ة—کڈپ‘وˆêژه‹`پAژ‘–{ژه‹`“Iگ¶ژYٹضŒW‚جٹQˆ«‚إ‚·پB•ْ‚ء‚ؤ‚¨‚¯‚خگâ‘جگâ–½‚جٹë‹@‚إ‚·پBژ‘–{ژه‹`‚ئ‚¢‚¤ژذ‰ï‘جگ§‚ھ‘¶‘±‚·‚éژ‘ٹi‚ھ‚ ‚é‚©–â‚ي‚ê‚é‚ج‚حپA‹°چQˆبڈم‚ة‚±‚ج–â‘肾‚ئژv‚¤‚ٌ‚إ‚·پB
پ@گخگىپ@‚µ‚©‚µپAŒ´”‚حژ‘–{ژه‹`‚جکg“à‚إ”pکF‚ة‚µ‚ؤ‚¢‚¯‚é“W–]‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚ثپB‚»‚ê‚ً‹°چQ‚ج‚و‚¤‚ةژ‘–{ژه‹`‚إ‚ ‚éŒہ‚è”ً‚¯‚ç‚ê‚ب‚¢‚à‚ج‚ئ“¯‚¶‚ةˆµ‚¤‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚é‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB
پ@•s”jپ@‚½‚µ‚©‚ةژ‘–{ژه‹`‚جکg“à‚إ‚à‚»‚ê‚ç‚ةˆê’è‚جکg‚ً‚ح‚ك‚邱‚ئ‚ح‚إ‚«‚ـ‚·پB‚»‚µ‚ؤژذ‰ï‚ھ‚»‚¤‚¢‚¤—ح‚ً‚à‚ء‚½‚ئ‚«‚ة‚حپAژذ‰ï‚»‚ج‚à‚ج‚à•د‚ي‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚·پBƒ}ƒ‹ƒNƒX‚ح‚»‚ج‚±‚ئ‚ًپAپwژ‘–{ک_پx‘و‚P•”‚جچإŒم‚ج‚ئ‚±‚ë‚إپAکJ“ژزٹK‹‰‚ھپuŒP—û‚³‚ꌋچ‡‚³‚ê‘gگD‚³‚ê‚éپv‚ئ‚¢‚¤Œ¾—t‚إ•\Œ»‚µ‚ـ‚µ‚½پBپuŒ´”ƒ[ƒچپv‚ج“¬‘ˆ‚إ‚àپA’n‹…‰·’g‰»‚ةژ•ژ~‚ك‚ً‚©‚¯‚铬‘ˆ‚إ‚àپA—کڈپ‘وˆêژه‹`‚ةکg‚ً‚ح‚ك‚ؤ‚ن‚گ¬‰ت‚ئ‚ئ‚à‚ةپAکJ“ژزٹK‹‰‚ئگl–¯‚ھ‚»‚¤‚¢‚¤—ح—ت‚ً‚à‚ء‚½گ¨—ح‚ة”“W‚µ‚ؤ‚ن‚‚±‚ئپAژه‘ج“IڈًŒڈ‚ھ’b‚¦‚ç‚ê‚éپB‚»‚±‚ةژ‘–{ژه‹`‚ج¢~‡£‚ً‘إ”j‚·‚邤‚¦‚إˆê”ش‘هژ–‚بƒ|ƒCƒ“ƒg‚ھ‚ ‚邱‚ئ‚ًƒ}ƒ‹ƒNƒX‚ح‚ ‚جŒ¾—t‚إ‹’²‚µ‚½‚ج‚¾‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB
ژj“I—B•¨ک_‚ج“TŒ^ژ¦‚µ‚½“ْ–{ژذ‰ï‚ج—ًژj
پ@گخگىپ@ژj“I—B•¨ک_‚جƒeپ[ƒ[‚ًگà–¾‚µ‚½Œم‚إپA•s”j‚³‚ٌ‚حپA“ْ–{‚ھƒ}ƒ‹ƒNƒX‚ج‚¢‚¤ژذ‰ï”“W‚جڈ”’iٹK‚ً‚ض‚ؤ‚«‚½“TŒ^“I‚ب—ًژj‚ً‚à‚ء‚½چ‘‚¾‚ئڈ‘‚¢‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ثپB’iٹK‚©‚ç’iٹK‚ض‚جˆعچs‚àپAٹO•”‚©‚ç‚ج‰e‹؟‚إ‚ح‚ب‚ژذ‰ï“à•”‚ج—ح‚إ”“W‚ً‚â‚è‚ئ‚°‚ؤ‚«‚½پA‚ئپB
پ@•s”jپ@‚½‚¢‚ؤ‚¢‚جچ‘‚حپAژذ‰ï‚ج”“W’iٹK‚ھ”ٍ‚ٌ‚إ‚¢‚é‚ج‚إ‚·‚وپB‚½‚ئ‚¦‚خƒQƒ‹ƒ}ƒ“–¯‘°‚حپA‹¤“¯‘جژذ‰ï‚جژ‘م‚ةƒˆپ[ƒچƒbƒp‚ةڈو‚èچ‚ٌ‚إ‚«‚ؤپAƒچپ[ƒ}‚ج“z—êگ§’éچ‘ژ‘م‚جŒoچد“IپE•¶‰»“IˆâژY‚ً‘S•”ˆّ‚«Œp‚¢‚إپA••Œڑگ§‚جژذ‰ïٹضŒW‚ً‚آ‚‚èپAƒhƒCƒc‚âƒtƒ‰ƒ“ƒX‚ج••Œڑچ‘‰ئ‚آ‚‚ء‚ؤ‚¢‚ء‚½‚إ‚µ‚ه‚¤پBƒQƒ‹ƒ}ƒ“–¯‘°ژ©‘ج‚ئ‚µ‚ؤ‚حپA‹¤“¯‘جژذ‰ï‚©‚çˆê‹C‚ة••Œڑگ§ژذ‰ï‚ة”ٍ–ô‚µ‚½‚ج‚إ‚·پB
پ@“ْ–{‚إ‚حپA‹¤“¯‘جژذ‰ï‚©‚çŒأ‘مچ‘‰ئ‚ةˆع‚ء‚½پB‚±‚ê‚حƒMƒٹƒVƒAپپƒچپ[ƒ}Œ^‚ئ‚حˆل‚¤پg‚ـ‚邲‚ئ“z—êگ§پh‚ً“y‘ن‚ة‚µ‚½چ‘‰ئ‚إ‚µ‚½پB‚»‚±‚©‚çچ‘“à“I‚ب•د‰»‚ً‚©‚¯‚ؤ••Œڑگ§ژذ‰ï‚ةˆع‚ء‚ؤ‚ن‚پB‚±‚جژذ‰ï‚ھٹ®گ¬‚·‚é‚ج‚ة‚حپA‚¸‚¢‚ش‚ٌ’·‚¢ژٹش‚ھ‚©‚©‚é‚ج‚إ‚·‚ھپA“؟گى–‹•{ژ‘م‚ة‚ـ‚إ‚ب‚é‚ئپA–‹––‚ة“ْ–{‚ة—ˆ‚½ƒCƒMƒٹƒX‚جڈ‰‘م‘هژg‚ھپA‚ـ‚é‚إ’†گ¢‚جƒCƒMƒٹƒX‚ئ‚»‚ء‚‚è‚»‚ج‚ـ‚ـ‚¾‚ئٹ´’Q‚جگ؛‚ً‚ ‚°‚½‚ظ‚اپAƒˆپ[ƒچƒbƒp‚ج••Œڑگ§‚ئ“¯‚¶‘جگ§‚ة“’B‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB
پ@‚»‚ê‚إ–¾ژ،ˆغگVˆبŒم‚حژ‘–{ژه‹`ژذ‰ï‚ض‚ج“]ٹ·‚إ‚µ‚ه‚¤،‚ـ‚é‚إ‹³‰بڈ‘‚ج‚و‚¤‚ة¤ƒ}ƒ‹ƒNƒX‚ھٹTٹ‡‚µ‚½ژذ‰ï”“W‚ج’iٹK‚ً‚·‚ׂؤŒo‚ؤ‚¢‚é‚ي‚¯‚إپA‚±‚¤‚¢‚¤—ًژj‚ً‚à‚ء‚½چ‘‚حگ¢ٹE‚ة‚ظ‚©‚ة‚ب‚¢‚ج‚إ‚·‚وپB
پ@ژRŒûپ@پwŒأ“T‹³ژ؛پx‚إ‚»‚ج‚ ‚½‚è‚ً“ا‚ق‚ئپAƒ}ƒ‹ƒNƒX‚ھژذ‰ï”“W‚جڈ”’iٹK‚ًگà–¾‚µ‚½‚ئ‚«پA‚±‚ê‚حپu‘ه‚أ‚©‚ف‚ة‚¢‚ء‚ؤپv‚جڈ‡ڈک‚¾‚ئ’f‚èڈ‘‚«‚ً‚µ‚½ˆس–،‚ھ‚و‚‚ي‚©‚è‚ـ‚·‚ثپB
پ@•s”jپ@ˆê‚آ‚ج–â‘è‚حپA“ْ–{‚ج—ًژj‚إ‚ ‚ç‚ي‚ꂽ‚ج‚حپA‹¤“¯‘ج‚»‚ج‚à‚ج‚ھژٌ’·‚ةڈ]‘®‚·‚é‚ئ‚¢‚¤پg‚ـ‚邲‚ئ“z—êگ§پh‚إپAƒMƒٹƒVƒAپپƒچپ[ƒ}Œ^‚ج“z—êگ§‚إ‚ح‚ب‚¢‚±‚ئ‚إ‚µ‚½پBژ„‚ح‚±‚ج–â‘è‚إ‚حپA‚P‚Xگ¢‹I‚ج––پAƒ}ƒ‹ƒNƒX‚جژ€Œم‚ج‚±‚ئ‚إ‚·‚ھپAƒVƒ…ƒٹپ[ƒ}ƒ“‚ھƒgƒچƒ„‚ج”Œ@‚إپAƒMƒٹƒVƒA‚جŒأ‚¢ژ‘م‚ج—ًژj‚ً‚ذ‚ç‚¢‚½‚±‚ئ‚©‚ç“z—êگ§‚جŒ©•û‚ة‘ه‚«‚ب•د‰»‚ھ‹N‚±‚ء‚½‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚آ‚ـ‚èپAƒMƒٹƒVƒA‚ة‚حپA‚ي‚ê‚ي‚ê‚ھ’m‚ء‚ؤ‚¢‚é“z—êگ§ژ‘م‚ج‘O‚ةپAƒ~ƒPپ[ƒl•¶–¾‚ئ‚¢‚¤ˆêژ‘م‚ھ‚ ‚ء‚½‚±‚ئ‚ھ‚ي‚©‚è‚ـ‚µ‚½،‚»‚±‚إ‚ح¤Œأ‘م“ْ–{‚ئ“¯‚¶‚و‚¤‚ةپg‚ـ‚邲‚ئ“z—êگ§پh‚جژذ‰ï‚¾‚ء‚½‚ج‚إ‚·پB‚»‚ê‚ھ•ِ‰َ‚µ‚½ŒمپA‚»‚ج•¶–¾“IˆâژY‚ًژَ‚¯‚آ‚¢‚إƒMƒٹƒVƒA‚ج“z—êگ§ژذ‰ï‚ھگ¶‚ـ‚ꂽ‚ي‚¯‚إ‚·پB
پ@‚»‚¤‚¢‚¤‚±‚ئ‚ھ‚ي‚©‚ء‚½–ع‚إگ¢ٹE‚ًŒ©‚é‚ئپAپg‚ـ‚邲‚ئ“z—êگ§پh‚ئ‚¢‚¤ژذ‰ï’iٹK‚حپA’†چ‘پAƒCƒ“ƒh‚ب‚ا‚جŒأ‘م‚جƒAƒWƒAڈ”چ‘‚âŒأ‘م‚جƒAƒtƒٹƒJڈ”چ‘‚ب‚اپAگ¢ٹE’†‚إ”Œ©‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پBƒˆپ[ƒچƒbƒp‚جگN—ھ‚إ•ِ‰َ‚µ‚½ƒCƒ“ƒJپAƒAƒXƒeƒJپAƒ}ƒ„‚ب‚ا‚à‚â‚ح‚肱‚جŒ^‚ة‘®‚·‚éŒأ‘مچ‘‰ئ‚¾‚ء‚½‚ئ‚ف‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@گخگىپ@“z—êگ§‚ئ‚¢‚¤‚ئƒXƒpƒ‹ƒ^ƒNƒX‚ج”½—گ‚ج‚و‚¤‚بƒCƒپپ[ƒW‚ھ‚ ‚ء‚ؤپA‚»‚ê‚ًٹîڈ€‚ة‚µ‚ؤ“ْ–{‚ج—ًژj‚ًگà–¾‚µ‚و‚¤‚ئ‚·‚é‚ئ–³—‚ھ‹N‚±‚ء‚ؤ‚‚é‚ي‚¯‚إ‚·‚ثپB
پ@•s”jپ@ژ„‚ح‚ق‚µ‚ëپAƒMƒٹƒVƒAپپƒچپ[ƒ}Œ^‚ج“z—êگ§‚ج•û‚ھپAƒMƒٹƒVƒA‚ج—ًژj‚ھگ¶‚فڈo‚µ‚½ˆê•دژي‚إ‚ح‚ب‚¢‚©پA‚ئ‚¢‚¤ٹ´‚¶‚ًژ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚ ‚ ‚¢‚¤ژذ‰ï‘جگ§‚حپA‚ظ‚©‚إ‚ح‚ب‚©‚ب‚©Œ©‚آ‚©‚ç‚ب‚¢‚إ‚·‚©‚çپB
پ@ژRŒûپ@کb‚ً•·‚«‚ب‚ھ‚çپAپwŒأ“T‹³ژ؛پx‚ة‚حپA‰ك‹ژپEŒ»چفپE–¢—ˆ‚جگlٹشژذ‰ï‚ج”نٹrک_‚ھ‚©‚ب‚葽‚‚ ‚ء‚ؤپAƒ}ƒ‹ƒNƒX‚ج—ک_‚ًگl—قژj‚جژ‹–ى‚إ‘ه‚«‚‚ئ‚炦‚³‚¹‚éچH•v‚ھ‚ ‚邱‚ئ‚ً‹‚ٹ´‚¶‚ـ‚·پB‚»‚¤‚¢‚¤‚±‚ئ‚à‚س‚ـ‚¦‚ب‚ھ‚çپA‚Q‚Pگ¢‹I‚ئ‚¢‚¤ژ‘مپAگl—ق‚ج–{ژj‚ة‚ق‚©‚ء‚ؤ‘«‚ً“¥‚فڈo‚·‚©‚ا‚¤‚©‚ئ‚¢‚¤ژ‘م‚ًپAگl—قژj“I‚بژ‹–ى‚إŒ©‚ؤ‚ن‚«‚½‚¢‚إ‚·‚ثپB
پ@پ\‘و‚QٹھپA‘و‚Rٹھٹ§چs‚جچغ‚ة‚àپA‚ـ‚½پA‚و‚낵‚‚¨ٹè‚¢‚µ‚ـ‚·پB