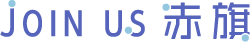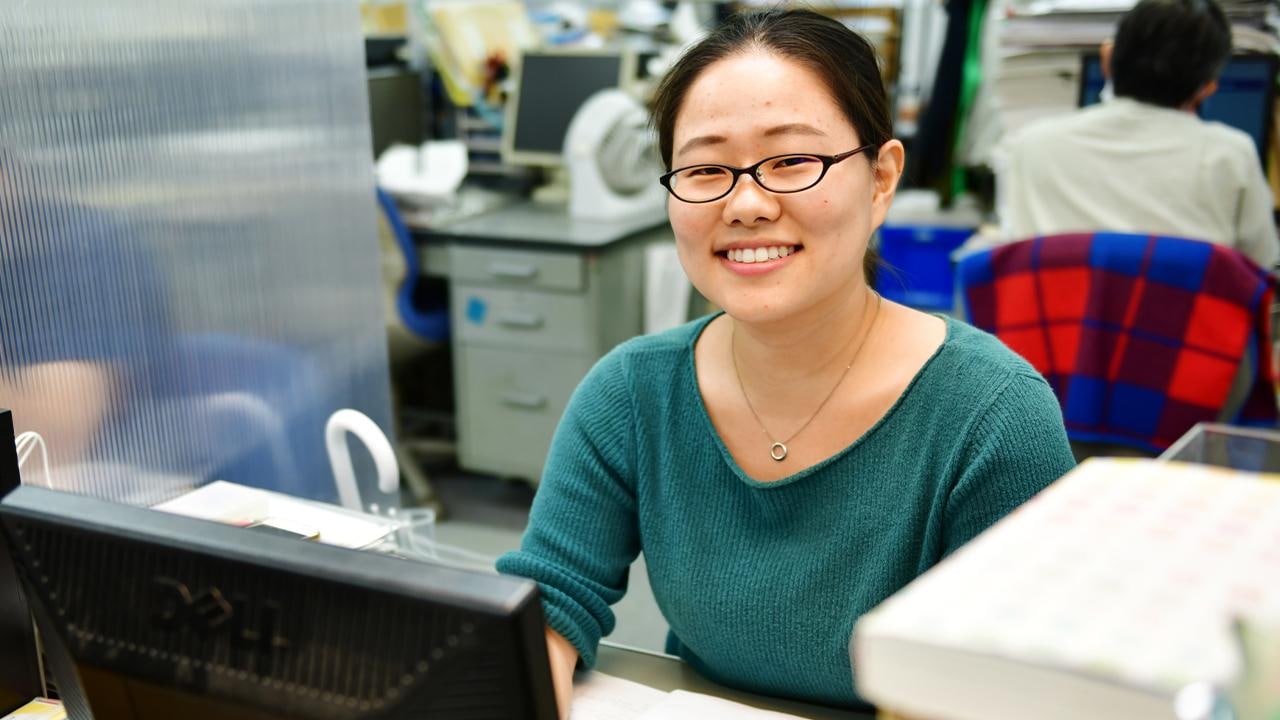原点は「弱者の声を届けたい」─記者として、人として
石黒みずほ(政治部記者)
私は幼少期から、両親が日本共産党員として社会的弱者のために献身的に活動する姿を見て育ちました。2人に連れられ多くの市民運動に参加する中で、「政治は社会的弱者のためにある」「幸せに生きる権利は誰にでも平等にある」と感じていました。
昔から身近にあった「しんぶん赤旗」の存在。手に取ると、そこには国の悪政や社会の不平等に対し、声をあげ行動する市民の姿が映し出されていました。権力者の動向ばかりを報じる大手メディアとは違い、日本・世界の出来事を〝市民目線〟で伝える「赤旗」の報道姿勢に感動すると同時に、「こういうメディアがなくなれば社会が大変なことになる」と危機感を持ちました。
2019年2月、米国での大学留学で培った世界的視野を生かし、社会的弱者の声を届けたいという思いで赤旗編集局に入局。校閲部に6カ月間所属し、同年9月から政治部の記者としてさまざまな取材にあたっています。
当事者に向き合わない文科省
政治部に入って2週間目の9月17日、取材で初めて現場に足を運びました。先輩記者に連れられ、タクシーで文科省へ向かう途中渡されたのは、日本共産党国会議員団による大学入試への英語民間試験導入の中止を求める申し入れ文でした。同年の臨時国会で大争点となった大学入試改革問題の先駆けとなる出来事となりました。
政府は、20年度から大学入試センター試験にかわって行われる大学入学共通テストで、英語の「読む・聞く・話す・書く」の4技能をはかるためとして、民間試験の導入を狙いました。しかし、民間試験は1回の受験料が高額なものを含むため、低所得家庭の生徒にとって大きな負担となる上、試験会場が都市に限られるため、地方や離島に住む生徒にとって不利となります。これらの経済的・地域的格差をはじめ、さまざまな問題があがっていました。
全国高等学校長協会や「〝入試改革〟を考える予備校講師の会」は、いち早くそれらの問題を指摘し、独自で実施したアンケートなどを基に、現場の不安や懸念、延期を求める声を届けてきました。英語教育や試験などの専門家らも署名を集め、導入中止を求める国会請願を行いました。
私が取材した申し入れでは、畑野君枝、宮本徹両衆院議員、吉良佳子参院議員が参加し、現場の声にしっかり耳を傾けるべきだと訴え。しかし文科省は、「民間業者に対策を検討するよう要請している」と責任を転嫁し、予定通り実施すると強行姿勢をみせました。
何の対策も講じられないまま、臨時国会が開会。繰り返し行われた野党合同ヒアリングには、教育関係者や高校生が駆けつけました。母子家庭の男子高校生や電話で参加した鹿児島県在住の女子高校生らが、当事者としての不安や怒りの声を突きつけましたが、文科省は「懸念を一つ一つ解消していく」との答えに終始。記者席にいた私は、勇気を出して声をあげる高校生に対し、結論ありきの態度で、真摯に向き合おうとしない文科省の姿勢に強い憤りを感じました。
声を上げる人がいるから変わる
しかし、これらの現場の声は、国会で追及する野党議員らの大きな原動力となりました。畑野氏をはじめ、立民の川内博史議員、国民の城井崇議員、無所属の山井和則議員は、文部科学委員会の質問や野党合同ヒアリングで一丸となって問題を追及。今年の通常国会で、新型コロナウイルス対応や検察庁法問題等の追及を通じて深化した野党共闘は、大学入試問題でも大きな力を発揮していました。
深刻な状況が続く中、19年10月24日、萩生田光一文科相が「(受験は)身の丈に合わせて勝負してほしい」と発言し、国民的批判が一気に広がりました。萩生田氏は発言を撤回しましたが、憲法が掲げる教育の機会均等を実現すべき文科相が、経済格差を当然視するとんでもない発言です。
畑野氏をはじめ野党議員は翌25日、導入延期法案を衆議院に共同提出しました。31日に行われた院内集会には、各党の国対委員長や他の野党議員らも出席。「大臣は言ったことを撤回できる。でも僕たちは、不当な基準の下で自分たちの大事な人生の節目を決められて、それはなかったことにはできない」。高校生らの力強い訴えに何度も拍手が起き、導入を延期に追い込もうと決意を固めあいました。
その翌日、萩生田氏は英語民間試験導入の「延期」を表明。同日行われた集会では、野党議員や高校生らが喜びを分かち合いました。安倍政権が大学入試改革のもう1つの柱としていた国語・数学の記述式問題の導入も、アルバイト等による短期間での採点で公平性・公正性がたもてないとして多くの問題点が指摘され、「見送り」に追い込まれました(12月17日)。市民と野党の共闘が政府による教育の改悪を止めた大成果です。
集会後に話しかけた女子高校生の言葉が今でも忘れられません。「今まで声をあげても何も変わらないと思っていたけど、声をあげる人がいるから変わるのだと思えた」。若者の中に広がる「政治は何もしてくれない」という〝政治不信〟。でも「声を上げれば必ず政治は動く」ということを、自らの経験を通じて語ってくれました。
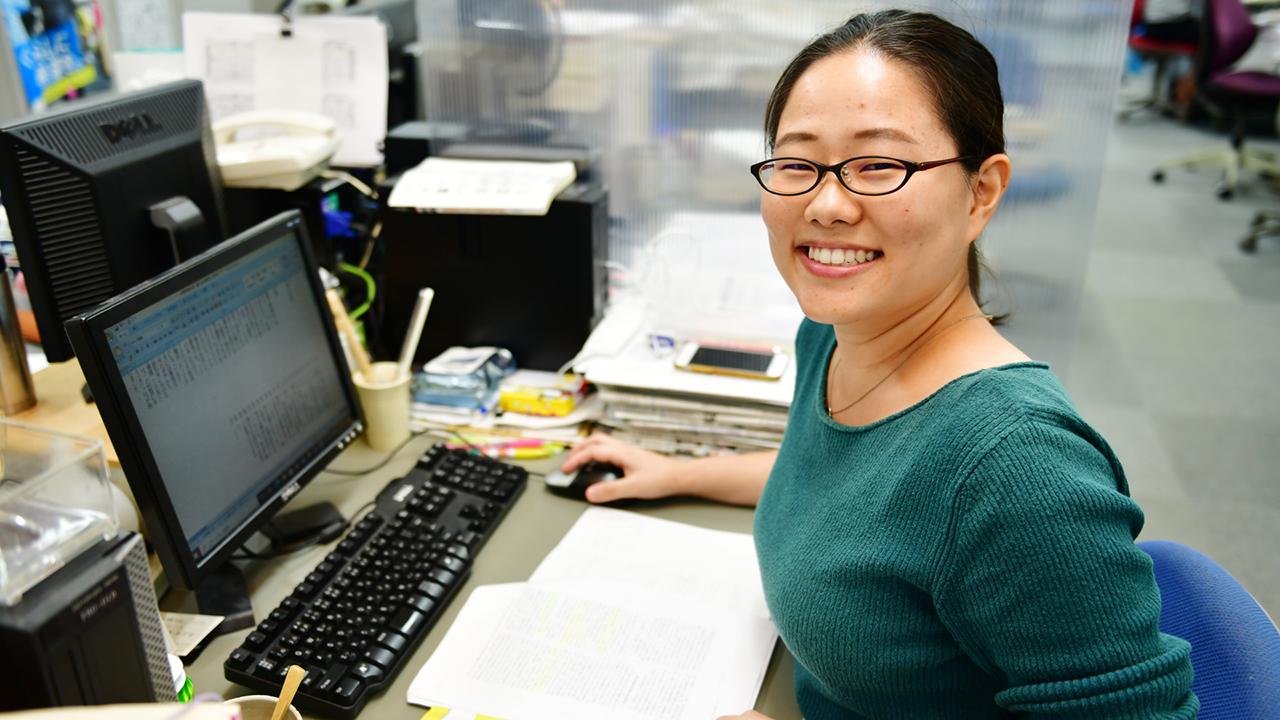
記者としての広島・長崎
臨時国会での取材を経て、今年から政治部の安保外交班となりました。在日米軍に関する問題、軍縮・平和運動を中心に取り上げますが、中でも印象に残っているのは、被爆75年をむかえた広島・長崎での取材です。小学6年生の時に広島で被爆体験を聞いた際、「核のない世界を、私のこの目で見るまでは絶対死ねない。必ずたたかい続ける」と涙ながらに語った被爆者の方の言葉が今でも頭を離れません。
赤旗記者として初めて訪れた被爆75年目の広島・長崎。被爆者は安倍晋三首相との面談で、自らの経験をもって核兵器の非人道性を訴え、唯一の戦争被爆国の政府として核廃絶運動の先頭に立つこと、核兵器禁止条約へ署名・批准することを求めました。
しかし、安倍首相は同条約について一切ふれず、核保有国と非保有国の「橋渡し」に努めると従来の主張を繰り返しました。実際には、安倍政権はトランプ米政権の核強化やアジアへの核配備を支持しており、「橋渡し」どころか、明確に核保有国の立場に立っています。何よりも、被爆国として核の脅威を伝え、核廃絶の先頭に立つべき立場にある国の政府が、「橋渡し」と称して〝仲介する〟こと自体が間違っています。
広島への原爆投下直後に降った「黒い雨」の被害をめぐる訴訟で住民ら84人全員を被爆者と認めた広島地裁判決についても、国は認めず控訴を決定しました。「被爆者に寄り添う」と言いながら、平気で被爆者の思いを踏みにじる日本政府が許せません。
しかし、世界に目を向ければ、核廃絶に向けた前向きな動きがあります。国連のアントニオ・グテレス事務総長は、国際的な核軍縮体制の保持・強化において、「その重要な一部となる核兵器禁止条約の発効を心待ちにしている」と平和式典にメッセージを寄せました。さらに、式典開催からわずかな期間で、新たに4カ国が同条約に批准し、発効は目前です。
「核のない世界」めざす一員
「若い世代の皆さん」─。田上富久長崎市長は「平和宣言」でこう切り出し、「あなたが住む未来の地球に核兵器は必要ですか」と問いかけました。原爆の惨禍を語った被爆者代表の深堀繁美さんも、最後に「若い人たちは、平和のバトンをしっかりと受け取り、走り続けてほしい」と訴えました。私は取材でメモを取っていましたが、何度も手が止まりました。被爆者が次つぎといなくなる中で、若者である私は、被爆者の経験を語り継ぎ、「核のない世界」を実現するための運動を進める一員であることに改めて気付かされました。
赤旗記者になった私の原点である、「社会的弱者の声を届ける」こと。それをしっかりと心に刻み、記者として、人として、成長していきたいです。
(いしぐろ・みずほ)