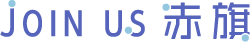暮らすことは生きること─今日よりちょっと素敵な明日のために

堤由紀子(くらし家庭部長)
生きていればいろいろなことが
「今日は何日ですか?」
私にとって、この問いに答えることほど難しいことはありません。「しんぶん赤旗」くらし家庭面は月、火、水、金、土(2ページ)の週5回。つまり〝曜日で仕事をしている〟からです。
「何の仕事しているの?」と友達から聞かれて「新聞記者なの」と答えると決まって「かっこいい!」「すごーい!」という答えが返ってきます。たぶん多くの方は「夜討ち朝駆け」「休みも返上して」走り回るイメージが浮かぶからでしょう。でも、くらし家庭部の記者活動はちょっと違う。それは「くらしの目線」が切り口になるからです。
「一見〝政治〟とは関係ないようでいて、光が当たっていない部分を取り上げたい」。くらし家庭面に人一倍愛情を注ぎ、精力的に取材を続ける記者はこう話します。「生きていればいろいろなことにぶつかる。本当はみんな政治につながっているんです。ただ、共産党の国会議員はまだ少ないから、何もかもはカバーしきれない面があって、そこを一つ一つという感じ。でも実際に取材してみると、実は党員の姿が見えたりしてほっとするというか、やっぱりすごいなあと思います」
「くらしの目線」から迫るには、アンテナを高く、広く張り巡らせることも大切です。日々、泉のごとく企画があふれ出してくる記者は「その時々の興味関心、私がやらなきゃいけないというテーマがあって、その中で新しい話やいい話をつかまえたら書く」と言います。ただ待つだけでは情報は飛び込んではこない。新しいつながりをつくるため、地道な努力を続けています。「学生のツイッターを見て、気になることをつぶやいている人がいたら、『もう少し詳しく教えてください』とダイレクトメッセージを送っています。遠くだとなかなか取材に行かれないけれど、どこでもつながれるネットはありがたい」
大学入試に関する一連の記事を通して、「赤旗なら」と信頼を寄せてくれる関係者とのホットラインも。「その人の手足になって取材して、記事を書いてます(笑)」。くらし家庭部の記者は他の面にも記事を書きます。入試改革を追うこの記者もその一人です。それぞれの記者が知恵を惜しみなく出し合う。部と部の間に垣根がないのも「赤旗」のいいところなのです。
問題が見える、肩の重みがとれる
「しんぶん赤旗」は記者の力だけでつくる新聞ではありません。読者の皆さんから学ばせていただくことが数えきれないほどあるのも、「赤旗」ならではの醍醐味です。
その一つが、1978年から続く「電話相談」。これは他紙にはないコーナーです。

日刊紙では「くらしの相談室」として毎週水曜を基本に掲載。日曜版には「赤旗電話相談」として、記事を提供しています。相談を直接受けるのは弁護士や税理士、社会保険労務士、元教員などの専門家。相談の場に毎回、くらし家庭部の記者が同席し、記者も原稿を書きます。専門的な知識が不可欠で、とりわけ神経を使う仕事でもあります。
「年金はその人によって全然違うので、その根拠を探すのが大変。〝落とし穴〟もたくさんあって、自分も結構はまっちゃうんです(笑)」。担当記者の一人はこう話します。いつ就職したか、あるいは退職したか、いつから保険料を払っているか、配偶者は何歳か...。「同じ事例が全くないし、旧年金制度の相談などだと回答者もすぐには答えられないこともあります。でも、記事が呼び水になって、また相談がくるんです」と。「しゃべっているうちに問題が見えてくるので、一人であれやこれや悩まずに、とにかく相談してほしい」と電話を心待ちにしています。
「電話だから相談者の姿は見えないけれど、声のトーンとかで相手の様子が伝わってくる」。電話相談の担当デスクはこう言います。「最初は泣いているような時でも、電話を切る時には元気になったりしたりすると、ほっとします。すっきり解決しないこともあるけれど、肩の重みがとれたのかなと。知らない人に相談するのはとても勇気のいること。電話をすること自身が前に踏み出したことになると思います」
一人一人の尊厳を守りたいから...
「くらし家庭面」では、ジェンダー平等が党の政策の中心にすわるずっと以前から、一人一人の尊厳を守るための記事を記者が丹念に取材し、記事として提供してきました。
性的マイノリティーのテーマにいち早く取り組んだのも、くらし家庭部の記者でした。「記事を載せたら、同性愛の当事者という人から『ずっと悩んでいた。党がこの問題に取り組んでいることに感謝する』という手紙が来ました」と振り返ります。「党内でも偏見があり、苦しんでいる人からの反応も多くありました。本当は悩みとか話し合っていける仲間のはずなのに、社会の問題が党内に持ち込まれていたんですね。それでも『赤旗』と党を信頼して、打ち明けてくれる人たちがいます」
この記者が心にいつも留めているのは「他人事にさせない」こと。「自分だって虹色の性の一人。個人の問題とせず、人権の問題としてみんなで社会を動かす方向にしたいです」
この思いを引き継ぎ、深めてきた記者は「苦しいとか、悩んでいるということを出すのも大事。でも何より、当事者は遠い国に生きてるんじゃなくて、あなたのすぐ近くで一緒に生きているんだよ、ということを想像してほしいと思った」と語ります。「一人一人を尊重し合って、お互いに自由に言い合える社会にしたい。言えない社会にしているのは私たち自身、だから社会の方を変えたい」と。「記事にするのはもちろんだけれども、当事者と会うことで党との懸け橋にもなれるんです」
人間としての尊厳が守られる社会をつくる。そのために大切なものの一つが性教育です。性と健康の問題に力を注ぐ記者のきっかけは「性のことを話すのはタブーという状態を変えたいと思った。自分もそうだったから」との思いでした。誰もが必ずかかわることなのに、ないものとしてしまって封じ込めている。「悲しい思いを一生引きずる人をなくしたいんです。朝から読む新聞にこういうテーマが載っていたら、タブーじゃないよとメッセージを送ることができると思います」
最近異動してきた若い記者は「ジェンダーをずっと追いかけたい」との熱意をもって、テーマと向き合います。その根っこには「マッチョがいい、というような〝男性性〟の中で生きるのが苦しかった」という自身の体験がありました。〝自分はこういうことを知っている〟みたいに、覇権を取り合うように競う。そこにすがろうとしたけれど、やっぱり生きにくかった...。「それとは違う社会を知って競争から早々に下りましたが、どこかで〝自分は落ちこぼれた〟みたいな気持ちを持っていた」と言います。「他者の困難に寄り添うという点では、党はとても強い。でも、自分自身の当事者性というか、自分が生きやすい社会にしたいということをもっと強調してもいいですよね」
みんな違うから面白い!
みんなが読みたくなる「赤旗」を作りたい。そのために記者の力を寄せ合うには、お互いを知ることも大事。しかも、日々の出来事が企画になる「くらし家庭部」では、とりわけおしゃべりが尽きません。(ご近所の部のみなさん、いつもお騒がせしてすみません)
新型コロナ感染予防策の一つとして、机の間にアクリル板が挟みこまれています。当初の心配もなんのその、このアクリル板をものともせず、おしゃべりの花が咲きます。「あーそうそう」「へーそうなんだ」「でもさー」。このおしゃべりが企画の〝種〟となり、芽が出て、葉を茂らせ、花を咲かせていきます。
週1回の部会も賑やかです。一人が企画を出すと、周囲がわらわらと話し始める。話はどんどん転がって、時には転がり過ぎて「で、なんだっけ?」と司会の私が議論の軸を見失うこともしばしば。でも、あちらこちらへ飛び跳ねるような議論こそが、くらし家庭面の命。部会が終わり、席に戻る間もおしゃべりは...。「頭が柔らかくなる」「雑談から企画が生まれる好循環」「みんなから意見が出るとやる気が出てくる」。数えきれない発見や共感を経て「くらし家庭面」へと実を結びます。
「たぶん赤旗編集局として最後の部署で、価値観が根底から変わった」。ぶっちぎりで超ベテランの記者は、自身を振り返ります。単身赴任時代は、パートナーから子育てでSОSがあっても、自分の仕事は崇高な任務だと思い「何言ってんだ」と突き放してしまった。この部にきて、いろいろな大変さを抱えながら働く人たちに囲まれて、「尊敬の念がわいた」と言うのです。「苦労しているからこそ人の見方が優しいし、ほめるのも批判もとても上手。本当の意味のリスペクトがあるから、みんなが話しやすいんだと思います」
暮らしぶりも生きる道も人さまざまです。がんがん頑張れる時もあれば、ほっこりしたい時もある。そんな〝揺らぎ〟もいいよねという紙面を作りたい、と強く思います。だからやっぱり記者の多彩さは譲れない。「みんな違うから、面白い」のですから。
ニュース部門をあちこち渡り歩いてきたベテラン記者は「くらし家庭部を希望して実現するまでに、20年かかっている。ほかの人とは年季が違う」と胸を張ります。短いニュース記事だと、捨てなければいけないものがたくさんある。「ずっともったいないと思っていました。何でも記事にできる、森羅万象の部です」
「潔いことばかり言っていてもダメ。まずはその人の生活から。おいしいもんでも食べよう。明日があるさ。そこが大事」。「くらし家庭面」の良さをこう表現した記者がいました。今日よりちょっと素敵な明日のための、エネルギー源。私たちは、あなたのすぐ隣に居続けたい。そう願いながら、今日もまたおしゃべりを始めます。
(つつみ・ゆきこ)