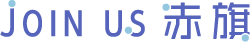ジョージ・フロイド事件と人種差別反対の抗議行動を追って

遠藤誠二(ワシントン支局)
戦没将兵追悼記念日明けの5月26日、米中西部ミネソタ州最大都市のミネアポリス警察が4人の警官を懲戒解雇にしたニュースが流れてきた。その理由が衝撃的だった。
SNS上にはすでに、このケースの全てが映像で投稿されていた。前日の夜、ミネアポリス市内の食料品店で偽造紙幣を使用した疑いで逮捕された黒人男性=ジョージ・フロイド氏が、後ろ手に縛られ地面にうつ伏せに倒された。その後、大柄な白人警官の左ひざがフロイド氏の頸部後ろを押さえつけた。「息ができない」との再三の訴えにもかかわらず、この警官は非情にも膝の圧迫を解くことはなかった。フロイド氏がぐったりした後も含め、約9分間それが続いた。
最後まで直視できないほどの残酷な映像。中学生の次女はSNS上でこの事件を知り自分の部屋から出てきた。「いったい何でこうなるの?」。家族が生活するのは、連邦首都ワシントン郊外のメリーランド州モンゴメリー郡。白人、ヒスパニック、アフリカ系、アジア系等、あらゆる人種がごったに暮らす地域で、娘は出身地や人種で差別を受けたことはない。「残念ながら、これがアメリカの別の姿だ。黒人への警察の暴力は後をたたない」と答えるのが精いっぱいだった。ミネアポリスもいろいろな人々が住む街なのだが...。
抗議行動は全米へ
全米、いや世界中で数千万の人々がこの映像を見て、衝撃を受けた。当然のことながら、ミネアポリスでは抗議行動が起きた。26日は、事件そのものと抗議行動の記事を外信面用のニュースとして送稿。そして何か、もやもや感が残る。このまま、地元で抗議が続いても、数日経てば海外ニュースにもならないほどのものになるのか。いや、「今回のケースはいつもと違うのではないか」との主旨を東京・外信部の当番デスクに伝えた。
ワシントンとミネアポリスは直線距離でも2000キロ近く。何度か取材で訪れたことはあるが、新型コロナウイルスの感染拡大で外出制限が続き、現地には行けない。27日には、地元で20年近く暮らす日本人ジャーナリストに電話をした。
警察署が燃やされ、近くの大型スーパーマーケットから様々な商品を抱えた人たちが出てくる。明らかに購入したとはみられない──彼女が見てきたことだ。抗議デモとともに、放火や略奪も発生していた。これが、ミネアポリスだけでなく隣町のセントポール、そして全米中に広がることになる。ショーウインドーは割られ、なかの商品は跡形もなくなり、街中、合成板でガラスが防御されたビルが立ち並ぶ荒廃した都市の姿がニュースで世界中に流れた。
しかし、今回の抗議行動の「主体」は決してこれら暴力行為ではない。平和的な抗議はその後、歴史を動かすものになる。
深い憤りと平和的に抗議
事件後、最初の日曜日となった5月31日。首都ワシントンでも抗議行動が各所でもたれた。ワシントンは人口70万の半数近くが黒人で、全米で最も黒人率が高い地域。小ぢんまりとした美しい町も、西側の裕福な市民が住む地域は白人がほとんどで、東側の比較的貧困世帯が多い地域の圧倒的住民は黒人と色分けされている。
抗議デモはその東側にあるハワード大学前で始まった。新型コロナウイルスの感染拡大が収まらないなか、平和的な集会とデモには大勢が集まった。黒人の青年たちに混じり、白人やアジア系の青年、なかには白人の教師もいた。「黒人の命は大事だ」「正義をわれわれに」─デモ隊の叫び声に、沿道から通行人、車のなかからドライバー、アパートのバルコニーから住民が呼応し唱和に加わった。これほどデモ隊と市民が一体となった行進はいままでみたことがないほど、感動的だった。
一方、話を聞いた黒人青年の言葉は深刻で胸を打たれた。「私たちの置かれた状況はこの10年、20年の話ではないのです」「奴隷が米国に連れてこられ401年経ちます。400年間、今も苦難を強いられているのです」
街でラップ音楽をガンガン鳴らし、声が大きく、屈託がなく明るいアフリカ系の人たちは、差別に憤り警察におびえ生活しているもう一面の姿があることを再認識させられた。
今回の件は、決してフロイド氏一人の死の問題だけではない。奴隷解放、公民権制定─。人権や人種差別をめぐる歴史的な歩みがある一方で、経済的な格差と教育、雇用、選挙権─などあらゆることで事実上の差別が今も続いているのが現実だ。新型コロナウイルスの感染拡大でも「格差」は顕著で、黒人の感染率は白人の2・5倍(APMリサーチ・ラボによる)、春に感染が爆発的に広がったニューヨークでは裕福な市民(ほとんどが白人)が町を逃げ出すなか、黒人やヒスパニック系の市民は地下鉄やバスに乗って働きに出て、多くが感染した。
そして警官による迫害。ミネアポリスでは2015年、16年にも警官による黒人市民の殺害が発生。今年2月には、ケンタッキー州ルイビルで、自宅で寝ていただけで令状なしに踏み込んだ警官により黒人女性が撃たれ殺された。フロイド氏殺害後も、南部アトランタで警官により黒人男性が射殺される事件が起きた。
民間調査機関「ペリーアンデム」が6月中旬に実施した世論調査結果には唖然とした。米国の黒人男性の実に45%が、自身か近親者が警官により銃口を突き付けられた経験を持ち、「警官がいると安全と感じない」と答えたのが72%にも上った。
31日、ハワード大学を出発したデモ隊は、ホワイトハウス前のラファイエット広場に到着。同広場ではフェンス越しに100人以上の警官隊が待機するなか、デモ隊の一人の黒人青年が同広場内に入りホワイトハウス方面に歩き出した。警官隊がその青年に向かう。一触即発の状況下で、別の黒人青年が必死に止めに入った。説得を受け後ろに引き返した青年に、周りから大きな拍手が沸いた。青年たちはむやみに暴力を好まない。無抵抗の人間を殺害する残酷な警官とは違う。
醜いトランプ政権の対応
こうした平和的な抗議行動とは正反対に、トランプ政権の対応は酷くすさんだものだった。5月29日、抗議デモ隊の一部がホワイトハウスに近づいたため、トランプ大統領はホワイトハウスの地下壕に逃げ込んだ。暴力に走った輩と平和的なデモをまとめて「極左グループ、テロリストの仕業だ」と罵る大統領は翌6月1日、デモに対処するため米軍の投入もためらわないと発表。その会見後、ホワイトハウス近隣のデモ隊を催涙ガスやゴム弾で蹴散らし、自身はセントジョンズ教会前まで出向き、聖書を右手に掲げた。聖書の名のもとにデモ隊を退治するメッセージを示した。暴力を行使したのは他ならぬ米国の最高指導者だ。
こうした行為は当然、各方面から非難を浴びた。一方で、デモ隊に緊張もはしる。「ほかをあたってくれないか?」その後、デモ参加者の声を聞こうにも、取材をことごとく断られた。こうした経験も米国では初めてだった。
しかし、事態はすぐ好転する。エスパー国防長官は3日、デモ隊への米軍の出動を「支持しない」と完全否定。ミレー統合参謀本部議長は、自身が大統領とともに教会に向かったことに反省を表明した。米国民の82%が平和的な抗議デモを支持する世論調査結果もでた(イプソス6月2日発表)。
5日には、トランプ大統領によってデモ隊が蹴散らされた通りに「BLACK LIVES MATTER」との文字が大きく書かれ、バウザー・ワシントン市長(彼女も黒人)が、「黒人の命は大事だ」通りとの名称を付けた。その後、青年のみならず多くの市民がそこを訪れ名所のようになった。黒人、白人、ヒスパニック、アジア系─「権力の象徴」=ホワイトハウス前で、肌の色がさまざまな青年が人種差別をなくそうと声をあげている。フェンスで封鎖されたホワイトハウスを市民が包囲しているかのようだ。社会の進歩を促進させる側、逆行させる側の姿がはっきり見えた。米国での記者活動は7年以上になるが、歴史の転換点を目撃したとなれば、「冥利に尽きる」と思う。

【写真】2020年6月19日、人種差別反対を訴えワシントン市内を行進する市民(遠藤誠二撮影)
主体は青年
連邦政府全体での警察改革は進む気配がなく、警察による黒人への迫害をなくすのは一朝一夕の課題ではない。さらに人種差別根絶という大きな問題に取り組むには、長い時間がかかると思う。ただ、今回のケースで、米国のみならず全世界で、人々の意識に変化がもたらされたことは確かだ。米国では奴隷制を肯定した南軍の司令官の像が撤去され続け、南軍旗の使用も禁止、奴隷制度を想起させるような名称の使用中止などが相次いでいる。
また、今回の取材を通じて強く感じたのは、気候変動対策の運動同様、一連の抗議行動の主体が青年だったことだ。初の黒人大統領となったオバマ大統領も、フロイド氏事件を受けた演説でこのことを強調した。その部分を少し紹介したい。
「私にとっての希望は、若い人たちが、奮い立って行動に移し、やる気を出して集まっていることだ。歴史的に、私たちの社会で起きた多くの進歩は若者がもたらしたものだ」「あなたたちは、怒りに駆られる時でさえ希望を抱くことができると私は期待する。なぜなら、あなたたちは物事をより良くする力があるからだ」
米国でも日々、たくさんのニュースがある。事象は絶え間なく起こる。問題があるのなら、そこには解決を求める草の根の人々の姿がある。それを追って報道する。時には地味かもしれないが、これは、赤旗記者としてはずせないことだと思う。
この間、日本の青年(民青同盟の地方組織)へ、ネットを通じて、フロイド氏事件と人種差別の問題での講座を数回持つことができた。他人事としてとらえない彼女・彼らの真剣な思いを感じることができて、とても嬉しかった。
(えんどう・せいじ)