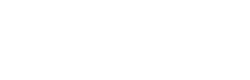67、少年法
少年法の適用年齢引き下げに反対します
2022年6月
2021年、第204回通常国会で、18、19歳を「特定少年」と新たに規定し、18歳以下の少年と区別して、厳罰化する内容の「少年法等の一部を改正する法案」が成立しました。
少年法改定の動きは、国民投票法を成立させるにあたって、投票年齢を18歳以上としたことに端を発し、公職選挙法の選挙権年齢やや民法の成人年齢の引き下げに合わせ、成人と同じように刑罰を科すべきだという議論から始まりました。
しかし、法律の年齢区分は法律ごとの立法目的により決められるべきものです。少年法は、少年の健全育成を目的としています。適用年齢の引き下げが少年司法にもたらす弊害は、あまりに大きいと言わなければなりません。少年法が果たしている役割について、改めて国民的な議論と理解を深めることが求められます。
日本共産党は、下記の理由から、適用年齢の引き下げに反対し、少年の健全育成を支える法改正を求めます。
18歳、19歳を「特定少年」とし、実質的に少年法適用から外すことは、少年の更生を妨げる。少年の非行を自己責任とせず、少年の更生を社会が支えるべきである。
現行少年法は、すべての事件を家庭裁判所に送致し(全件送致主義)、家裁や少年鑑別所における科学的な社会調査と資質鑑別の結果をふまえ、一人一人の少年に対する処遇を決定することとしています。
2019年に刑法犯とされた18、19歳は7,826人です(犯罪白書)。少年法の適用年齢が引き下げられれば、毎年数千人の少年は、事件の原因や背景について詳しく調査されないまま、社会に戻ることになります。親への指導や学校等との連携など、様々な教育的な措置が受けられなくなり、少年が抱える根本的な原因が解決されません。
非行少年は、その多くが生育環境や資質・能力にハンディをかかえています。少年院在院者の7割以上が家族などから虐待や暴力を受けた経験を持つとの調査もあります(法務総合研究所、01年)。こうした少年たちが更生し、社会に適応して自立していくうえでは、刑事訴訟的判断だけでなく、”人間科学”に基づき、個々の少年の要保護性を審判する福祉的・教育的手続きと処遇が必要です。そして、現行少年法のもとでの全件送致主義は、そのための有効な仕組みです。
しかし、少年法は2000年以降、少年審判への検察官関与制度の創設、重大事件を犯した少年を原則として検察官送致とする「原則逆送」(※)の創設、警察調査の導入、少年院送致年齢の引き下げなど、4度にわたる改悪が繰り返され、刑事訴訟化が進行してきました。このもとで、少年法の本来の理念である「少年の健全育成」や「成長発達権の保障」よりも、社会の処罰感情・応報感情を満足させることが優先される傾向が強まってきています。今回の法改定で「原則逆送」の対象犯罪が「短期一年以上」の事件へと大幅に拡大されました。
「少年だからといって甘やかすな。罪を犯した者は厳しく罰する方がいい」という意見も少なからずありますが、「少年法は少年を甘やかすもの」というのは、大きな誤解です。少年事件の多くを占めるのは、「万引き」「自転車泥棒」「ケンカによる傷害」「交通違反・過失運転致死」などです。それらが「成人並み」に扱われれば、被害金額の多寡や示談の成否などが酌量され、不起訴処分や略式命令による罰金刑によって終了するか、せいぜい執行猶予付きとなります。少年法適用年齢の引き下げは、罪を犯した18歳、19歳の反省と再犯防止・立ち直りに向けた十分な処遇を行わないまま放置することとなってしまうのです。ここで更生のチャンスを逃したばかりに、あとあとの大きな犯罪を防げなかったということにも、なりかねないのです。
今回の法改定で、起訴された段階で、推知報道が解禁されることになります。新たに原則逆送の対象となる罪も刑事事件となるため、起訴されれば推知報道が可能となります。少年の非行等がインターネット上に半永久的に残ることとなり、本人や家族に深刻な影響を与えます。
1948年の少年法制定以来、少年の実名や写真、住所など少年本人を特定する情報の公開により多くの好奇の目に晒すことは、少年の情操を害し社会復帰を妨げる危険性が大きいことから、報道を規制していました。本人が立ち直っても、好奇や偏見の目にさらされ続け、退学・退職をせざるを得なくなることは容易に想像できます。少年の家族が誹謗中傷を受ける可能性もあります。推知報道の解禁は、少年が更生し社会復帰するための教育、職業、家族の援助等という極めて重要な環境を奪うことにつながりかねません。
子どもの権利条約40条2項は、刑罰法規を犯したとされる子どもに対する手続のすべての段階子どものプライバシーの尊重を保障しています。また、少年司法運営に関する国連最低基準規則(北京ルールズ)8条も、少年のプライバシーの権利は、あらゆる段階で尊重されなければならず、少年の特定に結びつきうるいかなる情報も公表してはならないとしています。
また、「ぐ犯」(将来罪を犯すおそれがある少年。少年法では、①保護者の正当な監督に服しない性癖がある、②正当の理由がなく家庭に寄り附かない、③犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入する、④自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖がある、の4点をあげている)での少年院送致によって、しっかりとした指導を受け立ち直りの契機となる場合が多いのですが、今回の法改定で、18歳、19歳の少年は放置されることになります。とくに女子少年の場合は、このことで犯罪者や犯罪被害者になる懸念が強いのです。
※法改定前は、検察官への「原則逆送」は、16歳以上の少年が故意の犯罪行為で被害者を死亡させた場合で、裁判員裁判の対象にもなっている事件に限られていた。今回の法改定で「短期一年以上」の事件に拡大され、万引きをして逃げる際に追ってきた相手を振り切ろうとして怪我をさせた場合なども含まれることになる。
18歳、19歳を少年法適用の対象外とすれば、それを口実に少年犯罪の防止と少年の更生にとりくむ体制が大幅に弱体化されかねない
この間、少年犯罪は少子化を上回る規模で減少しています。凶悪犯罪も、昭和30年代半ばに殺人や殺人未遂で検挙された少年は400人台でしたが、近年は概ね50人と減少しています(少年全体)。「凶悪な少年犯罪が増えている。だから厳罰化が必要だ」という意見は、多分に印象によるものであり、客観的根拠はありません。
もちろん、だからといって、「少年犯罪は深刻な問題ではない」ということにはなりません。少年犯罪をとりまく環境は、貧困と格差の広がり、それにともなう家庭・地域の脆弱化、いじめや虐待の深刻化などから、困難さを増しているのも事実です。
こうしたもとでは、犯罪・非行の外形的な事実だけではわからない、一人一人の成育歴・成育環境や親の監護力などの事情を調べ、少年本人の更生と将来の犯罪予防に役立てることが、いよいよ重要となっています。
18、19歳は、就職や進学など自立に向けた人生を歩み始め、躓きに直面することが多くなる時期です。そのときに、少年法の適用年齢を引き下げたら、どうなるでしょうか。”重大な犯罪の芽を小さなうちにつむ”機会が大きく失われるばかりでなく、事件の背景を調査し、再犯や似たような犯罪の発生を抑止し、少年の更生を支える体制・機能が、ますます弱体化しかねません。
すでに、この間の4度にわたる少年法改悪で、少年審判の刑事裁判化と厳罰化がすすめられてきましたが、こうした中でも、少年法ではすべての保護事件について家裁調査官の科学的調査に基づくケースワークが行われ少年の立ち直りに向けた援助が行われています。子どもの育つ環境がいっそう困難なものになっているいま、少年法の理念と、それを支える体制は、決してこれ以上後退・弱体化させてはならず、むしろ充実させることが必要です。
年齢制限は、それぞれの制度や法の目的、社会環境などによって異なる基準があってしかるべきであり、他の法律とあわせるというだけの理由で、少年法の適用年齢を引き下げるべきではない
自民党は適用年齢引き下げの理由として「国法の統一性や分かりやすさ」をあげています。民法の成人年齢が18歳に引き下げられたことで、「一般的な法律において『大人』として取り扱われることとなる年齢は、一致する方が国民にとって分かりやすい」との意見などがあります。
しかし、この論理はすでに破たんしています。
選挙権は18歳以上に引き下げられましたが、同じ参政権に属する被選挙権は、現行の衆院25歳以上、参院30歳以上のままです。
飲酒・喫煙・公営ギャンブルに関しては、年齢制限の趣旨が健康被害防止と青少年の非行防止にあり、若年者の権利を拡大し自立を促すことを目的とした選挙権や民法の年齢引き下げとは趣旨が異なることから、一致させる必要がないとの意見(2018年5月16日衆院法務委員会での政府参考人答弁、同6月5日及び12日参院法務委員会での政府参考人答弁)を踏まえ、20歳以上が維持されました。
さらに、少年法自体についても、自民党自身が「成年年齢に関する提言」(自民党政務調査会、2015年9月17日公表)で、「罪を犯した者の社会復帰や再犯防止といった刑事政策的観点からは、満18歳以上満20歳未満の者に対する少年法の保護処分の果たしている機能にはなお大きなものがある」とその意義を認め、「若年者のうち要保護性が認められる者に対しては保護処分に相当する措置の適用ができるような制度の在り方を検討すべき」としています。実現性も定かでない「分かりにくい」制度を、提示せざるを得なくなっているのです。
* * *
この問題では、日本弁護士連合会が、会長とともに、47都道府県・52の弁護士会すべてで反対の声明を出しています。すべての弁護士会が反対声明を出すというのは異例のことです。現場の弁護士が、この間の相次ぐ少年法改悪によって少年法の理念がゆらぎ、激しい矛盾を引き起こしていることに、強い危機感を持っていることの反映です。
幅広い学者・研究者、家庭裁判所の調査官をはじめ、少年事件・少年非行に日常的に携わっている現場の専門家の方々も、こぞって年齢引き下げに反対を表明しています。
今回の改定法では、18、19歳を完全に少年法から除外せず、家庭裁判所の関与を維持しましたが、附則には「5年後に見直し」の条項があり、自民党などは、今後更なる「厳罰化」をすすめようとしています。
日本共産党は、世論と運動に連帯して、適用年齢の引き下げに反対し、少年の健全育成を支える法改正をめざします。