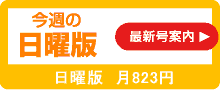2010年6月24日(木)「しんぶん赤旗」
「慰霊の日」
首相は「おわび」口にするなら
「基地の島」変えてこそ
菅直人首相は23日の「沖縄全戦没者追悼式」に出席し、「いまだに沖縄には米軍基地が集中し、大きな負担をお願いし続けている。そのような負担をかけてきたことに対し全国民を代表しておわびを申し上げる」と、「謝罪」しました。これは、所信表明演説(11日)で、同式典に参加し「長年の(沖縄の)過重な負担に対する感謝の念を深めることから始めたい」と語ったことに対する県民の批判を意識したものでした。
平和を脅かす存在
沖縄の地元紙・琉球新報の社説(12日付)は「謝罪ならまだしも感謝とは理解に苦しむ。感謝の言外に『今後とも負担をよろしく』と聞こえてならない。県民が求めているのは感謝の言葉などではない。これ以上犠牲や痛みを出さないという抜本的な政策の立案、実行である」と批判していました。
ところが首相は追悼式のあいさつで、「おわび」に続けて「他方、この沖縄の負担がアジア太平洋地域の平和と安定につながってきたことについて率直にお礼の気持ちも表させていただきたい」と、再び「感謝」を表明したのです。
それは、戦後65年間、沖縄に耐え難い犠牲と痛みを強いてきた米軍基地が「アジア太平洋地域の平和と安定」に役立ってきたとし、この負担を今後とも県民に押し付けようとする意思表示です。
しかし、首相はかつて、沖縄の米軍基地の大半を占める海兵隊が「ハワイやサイパンなどに移転してもアジアの軍事バランスには影響しないはずだ」と指摘。民主党中心の政権になれば「海兵隊の沖縄からの撤退を真剣に検討するよう米国にはっきり求めていく」と述べていました。(『現代』2002年9月号)
沖縄の基地負担の元凶である海兵隊は、菅首相も過去には認めていたように、「地球の裏側まで飛んでいって、攻める部隊」(06年6月1日の講演)であり、侵略部隊です。「アジア太平洋地域の平和と安定」に貢献するどころか、逆にそれを脅かす存在です。首相はかつての発言を思い起こすべきです。
悲しい記憶忘れず
首相は、沖縄の普天間基地(宜野湾市)の県内「移設」=名護市辺野古への新基地建設を進め、新たな犠牲と痛みを強いる日米合意をあくまで推進しようとしています。首相はあいさつで「沖縄の負担軽減」を強調しましたが、むなしく響くばかりです。
追悼式で普天間高校3年生の名嘉司央里さんは、「変えてゆく」と題した詩を朗読しました。
当たり前に基地があって/当たり前にヘリが飛んでいて/…普通なら受け入れられない現実を/当たり前に受け入れてしまっていた/これで本当にいいのだろうか/…忘れてはならない/この島であった悲しい記憶/目を背けてはならない/悲しい負の遺産/それを負から正に変えてゆく/それがこの遺産を背負い生きてゆく/私たちにできること
「基地の島」という「受け入れられない現実」「悲しい負の遺産」を変えていく―。首相が「戦没者の尊い犠牲を忘れてはならない」と言うなら、日米合意は白紙に戻し、普天間基地の無条件撤去に踏み出すべきです。(榎本好孝)
■関連キーワード